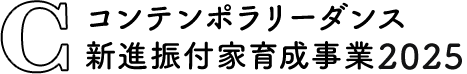KCA2022振付家インタビュー⑥ 大森瑶子
「ただ、自分が助かりたいがため」に踊る
掲載日:2023/01/10
聞き手:鄭慶一(アートマネージャー/プロデューサー)

|
「エキストラ」が表現するものの変遷 鄭: まず初めに「どうして大森さんがコンテンポラリーダンスの道に進んだのか」をお聞きしたいのですが、もともとクラシックバレエをやってらしたんですよね? 大森: そうです。5歳くらいから12歳くらいまでやっていました。その後に中学と高校のダンス部でダンスをコーチから教わって、そこで「自分でつくるのも楽しそうだな、コンテンポラリーダンスって楽しそうだな」と思い始めました。 鄭: その時はコンテンポラリーダンスも誰かから教わっていたんですか? 大森: はい。私は日本女子体育大学出身なんですが、その先輩の高橋萌登(たかはしもと)さん がコーチとして来てくれて、部活でコンテンポラリーダンスやヒップホップも教えていただき、非常に影響を受けました。大学では仲間と作品をつくったり、自分個人でもつくったり、他の人の作品に出たりと学内の活動が中心でした。その大学を卒業して、現在4年目です。 鄭: 少し今回の作品のことに触れていきたいのですが、今回の作品、僕は非常に面白かったんですよね。作品を見ながらけっこう笑ってしまったほど。いちばん面白かったのが「エキストラ」という存在。あの「エキストラ」というのは、一般的な意味でエキストラだからそう呼んでいるのか、あえてあの存在たちを「エキストラと呼ぶことにしている」のか、どうなんですか? 大森: 最初から「エキストラ」という役割で、自分以外の6人を出演させようという意図で作品をつくり始めました。 鄭: 「エキストラは私の雑念のようなもの」と作品紹介のテキストで大森さん自身が語っていますが、僕には彼女らが大森さんと同列・並列の存在に見えたんですよね。「自分が何かに依存する」ということや「すがりたい」という気持ちを犬のポーズや鳴き声で表現している一方で、その依存(大森さん)と雑念(エキストラ)のバランスが、もはや同列・並列のものとして調和して見えた。だから「全然エキストラじゃないな!」と思って(笑)。これは悪い意味ではなくて、もはやこの「エキストラ」がいないと作品が成り立たなくなっているなと。そういう心理バランスなのかなと思って見ていたのですが、いかがですか? 大森: そうですね、エキストラは「雑念」なんですが、「依存」ということは、エキストラはさほど担っていないです。最初に「エキストラ」という役割を置いたときには「いてもいなくてもいい存在」として設定していましたが、今回のKYOTO CHOREOGRAPHY AWARDで3回目の上演となるこの作品「Help」は、回を追うごとに次第にエキストラの存在が強くなってきていて、やりたいことも増えてきています。初期の頃は、私が踊っている傍らで、本当に映画のエキストラのように誰がそれをやってもいいくらいの存在として明らかに脇役だったんです。ですから「なんだか雑念みたいな感じだなぁ」というふうに結び付けて、「エキストラ=雑念」という言葉で表現していたのですが、その役割が徐々に変わってきて、「もはやエキストラじゃないかもな」と思い、今回からはエキストラではなく「出演者」として登場させています。 鄭: 最初に「エキストラ」が舞台に出てきた時のインパクトが衝撃的でした。「あ、出てきた…と思ったらいなくなった!」みたいな(笑) 大森: 最初はエキストラを「舞台美術」の一つのように考えていた所もありました。 鄭: 確かに舞台美術として捉えると分かりやすいと思いました。おそらく観客もそういうふうに見ているでしょうし。その中でも、なんとなくエキストラの役割が一人一人決まっているじゃないですか。それはあらかじめそのように設定していたんですか? このエキストラはこの雑念、こっちのエキストラはこの雑念、みたいな感じで。 大森: 感覚的に「シャワーを持っている人がほしいな」とか「着替えている人がほしいな」みたいな感じで役割をつくっていったので、自分自身の実際の雑念とそんなにリアルに結び付いているわけではないです。でも「一人一人の持っている役割からはみ出さない」というルールは決めてあって、その役割は一人一人設定してあります。
|
 バレエコンクールにて 2007年  「Help」photo: Nora Houguenade
|
|
「ネガティブなもの」を「見せられるもの」にする強さ 鄭: この作品をなぜつくろうと思ったのかを伺いたいのですが、作品のコンセプトをテキストで読んだ時の印象と、実際の舞台の映像を見た時の、ある種の「ポップさ」みたいなものとのギャップが、僕の中では非常に興味深いんです。大森さんがどんな心理状態でこの作品をつくろうと思ったのかを知りたくて。 大森: 私はそもそも作品をつくる時に、自分以外の何かの事柄をテーマにしたいと思ってつくるタイプではなく、自分の中にある個人的な出来事から派生していってつくることが多いんです。それもネガティブなことを起点にする方が圧倒的に多い。ほぼ全部の作品がそうだと言ってもいいかもしれません。例えば私生活で何か悲しいことがあって、そこから「あ、これは依存だな」みたいな気づきからどんどん膨らませていってつくるんです。 ただ、つくる時に、見え方というかビジュアルは非常に気にするので、それが先ほどおっしゃっていた「ポップさ」みたいなものにつながるのかなと思います。私的でネガティブなテーマを作品にした時に、完全に内側にこもって…というのではなく、人が見ていて単純に面白いものにしたいという思いがある。そこが確かに対照的なのかもしれないですね。自分のネガティブな感情と、見た目に面白いものをつくりたいという思いが、同時に存在している所があります。 鄭: その「ネガティブなものをアウトプットしたい」ということなのか、「ネガティブなものしかアウトプットできない」ということなのか、または「ネガティブなものをアウトプットせざるを得ない」なのか、そこがとても気になります。いかがですか? 大森: 「せざるを得ない」のかもしれないです。私自身がとてもネガティブな性格だから、ネガティブな出来事があると、どんどん自分の内側へ内側へと入っていってしまう。「助かりたいがために踊る」というふうに書いていますが、それが最も本心に近くて、自分の心が助かりたいがために作品をつくることがいちばんの動機かもしれません。 鄭: なるほど。その「助かりたい」という気持ちが作品や踊ることであるというのは、いつ頃からですか? 大森: 大学の後半の3~4年生ぐらいからです。ちょうどその頃からコンテンポラリーダンスの作品をつくり始めたので、わりと当初からそういう感じです。 鄭: 「助かりたい」って、どういう感じなんでしょう? 大森: 「助かりたい」というのは、私はもう究極的には「死にたい」ぐらいまでネガティブな方へ行ってしまうので、純粋に「いや、死にたくない。生きたい」みたいな感じです。 鄭: それは、しんどくないですか? 大森: しんどいです(笑)。 鄭: その「しんどいもの」を、これだけ「見せるもの」にする大森さんのエネルギーの凄さを、今改めて僕は感じているんですが、作品をつくる時、大森さんはどういう気持ちなんだろう? 「助かりたい自分」を引き上げて作品にするのも自分だから、そのモチベーションはどこなんでしょうか。自分を助けている過程も自分だから。 大森: 確かにつくっている間はずっと「しんどい」がベースではあります。でも、それを発表した時に誰かに見てもらえるから「助かることができる」し、頑張れる。その発表する日だけをモチベーションにやっていますね。 鄭: 凄いな。それがなぜ「ダンス」だったんでしょうね? 大森: 今までダンスしかやっていなかったからだと思います。 鄭: 少し意地悪な聞き方かもしれませんが、もしダンス以外で助かった場合、どうするんだろう? 大森: そしたら、ダンスをしなくなると思います。 鄭: それは凄いことですよね。僕はわりと分散してしまうんです。しんどいことを、いろいろな方法で。自分の中にセーフティーネットをたくさん持っている状態。逆に僕は、その助かる方法をたくさん持っている状態が無くなるとしんどいんですよね。それが大森さんみたいにもし一つだけだったとしたら、僕は生きていけないと思いました(笑)。見方はいろいろあるかもしれませんが、そこにはおそらく「強さ」みたいなものがあると思うんです。セーフティーネットが一つというか、「これのために生きられる」というのがあるというのは、とても強いことだと思います。 このお話を伺って、今改めて作品を振り返ると、もしかしたら僕が感じた「ポップさ」みたいなものは、その「強さ」なのかもしれない。「ネガティブなもの」、「助かりたい」みたいな比較的暗いテーマを、「見せるもの」にするためにあのような構造や形になっているとおっしゃっていましたが、自分の暗いテーマ・コンセプトを、面白く見られるものにするという強さは凄い。そういう「助かりたい」というモチベーションでダンスをつくったり、踊ったりしている中で、大森さん自身が楽しいと感じる瞬間はありますか? 大森: 楽しい瞬間はあります。単純な話ですが、振り付けをつくるのが好きなので、面白い振りができた時は自分自身も楽しい気持ちになるし、稽古中にエキストラのみんなと「こうしよう、ああしよう」と試行錯誤して面白い場面ができた時は楽しくなります。 鄭: 大森さんはご自身の作品を、映像などで客観的に俯瞰して見たいと思うタイプですか? 大森: はい。 鄭: その時はどういう気持ちなんでしょう? 大森: いろいろな気持ちになります。単純にここの部分のダンスが面白くないなとか、ここの間が良くないなとか、構成がつまらないなとか、そういう見方がほとんどです。 鄭: 大森さんの作品の場合、ごくパーソナルなものが舞台の上に乗っているような気がするのですが、それが人にどう見られるのかを考えたりするのかな。 大森: そういう見方をしようと思って映像を見返すこともありますが、やはりどうしてもパーソナルな部分を客観的に映像で見て感じるというのは難しいです。 鄭:「観客がどういうふうに見るだろう?」というのは、言い換えると、観客に何を持って帰ってほしいと思っているか、みたいなことかもしれませんが。 大森: それは実は今の私の課題でもあるんです。去年の横浜ダンスコレクションでも「もう少し観客と共有し合える空間をつくった方がいいよ」とアドバイスをいただきました。構成や展開を客観視する見方だけではなく、「観客にどう受け取られるのか」ということも考えられるようになるのが自分の課題だと思っています。 鄭: なるほど。僕は個人的には、それは全然しなくていいと思っているんですが(笑)。僕はこの作品がすごく面白かったんです。いろんなことを考えさせられた。「ネガティブなもの」を自分が助かりたいがために「見せられるもの」にしようとしたら、こういうものが出てくるんだという面白さ。これが逆にすごくテクニカルに考え抜かれたものだと、意図が透けて見えて白けてしまう気がするんです。その点でいうと、後半は僕はあまり笑えなかった。前半はポップでキャチーですごく良いんだけど。
|
横浜ダンスコレクション「甘いの、ゾルミ」(横浜にぎわい座のげシャーレ、2020年) photo by Oono Ryusuke  DANCE×Scrum!!! 2020 「ERROR」(池袋あうるすぽっと、2020年)_photo by bozzo
 稽古の様子 |
|
感覚的に「面白い」を捕まえていく 鄭: 作品の構造の話を少し伺いたいのですが、最初は小さい手の動きだけで踊っていて、少しずつ大きくなっていきますよね。どうしてあのような構造なんでしょう? 単純に気持ちとか、感情の表現なのかな? 大森: 最初の場面は、緊張感のあるシリアスな場面にしようとだけ決めてありました。その時期にちょうど手だけでインプロをしていたら私自身が面白かったから、これは手だけで何か見せられるかもしれないと思ったことがきっかけです。だから特に「感情」ではないですね、構成的に考えてその振り付けにしたという感じです。 鄭: 非常に良いですよね、あそこで大森さんにフォーカスが集まりますよね。エキストラが入ってくるタイミングは、なぜあのようなタイミングだったんですか? 大森: あれはこの作品をやろうと思った時に、最初に思い浮かんだシーンです。「眠りの森の美女」の曲で、最初の7、8分は私だけしかいなくて、あのちょっと無音の所で6人一斉に入ってきたら面白いなというのが最初に浮かんだので。 鄭: その「面白いな」というのは、どういう種類の面白さなんですか? 大森: どっちの意味もあります。興味をそそるという意味と、滑稽だという意味と。 鄭: あの場面を何度もリフレインしてしまいます。今回のKYOTO CHOREOGRAPHY AWARDに向けて再びこの作品をブラッシュアップするんですよね。どういう方向へ変えていきたいですか? 大森: 「エキストラ」と呼んでいる他の出演者たちを、もっと動かしてみたいという思いがあります。今はまだ構成をつくっている段階ですが、場面展開をさせるシーンをつくったり、私もエキストラの一人になる場面もつくったり、後半のシーンを少し長くしようかと考えています。 鄭: 大森さんが舞台の上手からいつの間にかいなくなって、エキストラだけが残るシーンがありますよね。そこもとても好きなシーンですが、どうしてあのようなシーンをつくろうと思われたんですか? 大森: あれも単純に面白いかも、という感覚です。 鄭: 面白かったが故にすごく考えてしまいました。なんでだろう?って。 エキストラだけになっているそのシーンがあったので、僕は「依存」と「雑念」とが併存して、もはやどちらもないと成立しなくなったのかと考えましたが、そんなことでもなく「単純に面白いと思ったから」という理由なのが余計に凄いです(笑)。
|
 「Help」photo: Nora Houguenade  「Help」photo: Sugawara Kota
|
|
個人的なたった一つの「悲しい」が作品になることの美しさ 鄭: 大森さんの作品は、今後いろんなアプローチができる可能性がある気がしています。今後作品をつくり続けていくにあたって、大森さんは今どんなことを考えていますか? 先ほどおっしゃっていたように個人的な出来事が作品の起点になるのであれば、自分の在り方や内面が変わっていったりすると、作品をつくり始める動機も変わってくるんじゃないかと。何か最近の心境の変化などはありますか? 大森: そうですね、この作品は去年の夏ぐらいにつくりましたが、最近はあまり大きな変化がなく、逆に「ネガティブ不足」になっていて、どうしようって(笑)。 鄭: それは厄介ですね(笑)。「ネガティブ不足」で作品がつくれなくなるかもしれないんですね。 大森: もちろんこういう状態でも作品をつくったことはあるので、違った作風になるだけで深刻に悩みすぎることはないんですが、何か「不幸な要素」はほしいなという気持ちはあります。 鄭: そこで不幸を求めに行かなきゃいいなと思っているんですが(笑)。めちゃくちゃポジティブな心境の時に作品をつくったこともあるんですか? 大森: あります。大学の時に。 鄭: ちなみにどうでした? ご自身としてその作品は。 大森: 大学の頃は曲をたくさん使って、ほぼ踊りだけで展開していく作風でつくっていたんです。大学を卒業してからはずっとネガティブな感じなので、卒業後はポジティブな状態ではつくっていないかもしれない。 鄭: そのネガティブは、何かに対する不安だったりするんですか? 大森: そうですね、不安とか、怒り、不満、依存、依存からくる悲しさ…「悲しい」がいちばん大きいかもしれないです。 鄭: 差し支えがなければ伺いたいのですが、どんな「悲しい」が作品になったのでしょうか? 大森: 単純に恋人と別れたとか、とても個人的なことです。それが大きいですね。 鄭: それは一つの「悲しい」なのか、いくつかの「悲しい」が重なって爆発したのか、どうなんでしょう? 大森: 一つの「悲しい」です。 鄭: 大森さんが作品をつくっている時は、本当にとても悲しいんだろうな。 大森: そうです。 鄭: それを笑って「そうです」と言っているのが凄いですよね。羨ましいと思うのは、多くの人がそうかもしれないですが、そんなにモチベーションにするものが無いと思うんです。もちろん人にもよると思いますが、ひと昔前までは、なんとなく働いていればなんとなく幸せになれたけれど、今はそうでもないし、選択肢がたくさんある中で「これのために頑張れる」というものがなかなか無いと思うんです。その中で、大森さんの、その一つの「悲しい」が作品になること、しかもそれが明確であることがとても羨ましいなと思いました。 僕たちはこういう業界にいるから作品をつくったりしていますが、社会を見ていると、何かにモチベーションを持つということをしている人自体が少ないように思えるし、逆にできなくなってしまっているんじゃないかと思います。なんとなく標本もあるし、先が見えてしまっているという気がする。そんな中で、大森さんのようなモチベーションで作品をつくっていることを、この業界に限らずそういう人を僕は羨ましいと思うし、美しいと思います。他人の「悲しい」を美しいと言うのもどうかと思うけれど。今後もこういう自分の内面的なものをモチベーションに、作品をつくっていきたいですか? もちろんどんどん変化していくものだと思いますが。 大森: 私の根底にずっと「今の自分をどうにかしたい」という思いがあります。ダンスに限らず、私はそれがベースで生きているので、それをベースにつくり続けるのかなと思います。舞台に立っている時も、「この場をどうにかしたい」と思いながら踊っているんです。舞台上のこの時間を。 鄭: 自分をどうにかしたいというのは、明確に「こうなりたい」というものがあるわけでもなく? 大森: そうです。何か「どうにかしたい」。 鄭: 現状が不満なのかな? 大森: そうですね、何が不満なのかもよく分からないですが、ずっと常に不満というか、なんとなく「嫌だな」という感じです。 鄭: 分かったつもりになっている人よりずっと良いと思います。5年後とかに大森さんが「あの頃の私はなんだったんでしょうね?」みたいにめちゃくちゃポジティブになっていたら面白いなと思うし、でも、ずっとそのままでも面白いと思います。 |
|
|
振付家 大森瑶子(オオモリ ヨウコ) 作品概要「Help」 この作品のテーマは、「犬」そして「ただ助かりたいだけ」である。 私は、人や物や何かに依存していないと生きていけない、どうしようもない人間である。最近、その依存してい たものが遠くに行ってしまったことで、酷く絶望し、とにかく助かりたいという気持ちになった。 「犬」というのは、私の心情を表すシンボルである。インターネットで、「人の心は犬や猫くらい馬鹿なのかも しれない」という内容のものを見つけた。私の心情は複雑で重く思えたが、犬と同じくらい単純なのかもしれない。「誰かに何かにすがりたい依存したい執着したい、でも本当はただ助かりたい」という根底の心理を犬のポーズや鳴き声で代弁させている。 また、エキストラとしている大森以外の出演者達は、ただただ私の心の中を6人の人間で表しており、作品内容に特に意味をもたらしてはいない。私の雑念のような存在。 インタビュアー 鄭慶一(チョンキョンイル) アートマネージャー/プロデューサー。1986 年北九州市生まれ。在日コリアン 4世。立命館アジア太平洋大学卒業。2012年より福岡県の民間劇場「枝光本町商店街アイアンシアター」の運営に携わる。2013 年同劇場ディレクターに就任。主にコンテンポラリーダンス、ビジュアルアートに携わり、野外ダンスフェスティバル「枝光まちなか芸術祭」(2013 年∼)を主宰・ディレクションする。国内外多数のダンサー、 カンパニーとの共同事業を行うと共に、様々なアートプロジェクトに関わる。
|
|
|
「KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2022ー若手振付家によるダンス公演&作品を巡るディスカッションー」 Interview |