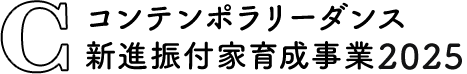KCA2022振付家インタビュー⑤ 女屋理音
「言語化できない何かを共有する宿命」を創造する
掲載日:2023/01/05
聞き手:森嶋拓(プロデューサー・北海道コンテンポラリーダンス普及委員会委員長)

|
コンテンポラリーダンスとの接点 森嶋: 女屋さんの作品は見た瞬間に安心したというか、作品の完成度、総合力がとても高く、コンテンポラリーダンスをよく学んでいる人だな、これまでたくさん作品を観てきた人なのかなと感じました。それで年齢を見たらとてもお若いので驚きました。「どうしたらこういう人が育つんだろう?」って(笑)。これまで数多くの作品を見てきたんですか? コンテンポラリーダンスをするようになったきっかけを教えていただけますか。 女屋: 元々はクラシックバレエを群馬県で習っていて、私のスタジオの主宰の先生の娘さんがヴッパタール舞踊団にいらっしゃる瀬山亜津咲さんという方なんです。亜津咲さんが、私が小学生くらいの時からスタジオにワークショップに来てくださっていて、先輩方がピナ・バウシュのダンスフェスティバルに参加して実際にピナに会うなど、ヴッパタール舞踊団との交流というか、つながりがあったんです。ですから私は小学生くらいからずっとピナ・バウシュの作品を見る機会が多く、衝撃を受けたと言いますか、コンテンポラリーダンスという世界があることを幼い時から知っていたという背景があります。 それから、いちばんのきっかけは、高校生の時に亜津咲さんの旦那さん、元ヴッパタール舞踊団のファビアン・プリオヴィルさんの作品「紙ひこうき」に出演したことだと思います。出演するにあたり、ダンスシアターの作品創作のプロセスや、「踊らない体で舞台に立つ」と言いますか、独特の立ち方や舞台上での在り方などといった少し特殊な道、いわゆる技術的な所からではなく作品性から入ったという経緯は、私のダンスに影響を与えていると思います。 本格的にテクニックを習い始めたのは大学に入ってからです。お茶の水女子大学に入学し、大学ではそれほど実技の授業はなかったので、私は外部の、マーサ・グレアム舞踊団やマース・カニングハム舞踊団などのいろいろなテクニックを組み合わせてやっている先生の所へ習いに行くことが多かったです。今もそうですが。私のコンテンポラリーダンスに触れた歴史としてはそのような感じです。 森嶋: ある意味、日本ではとても特殊な環境ですね。では大学から東京に住んで、そこからいろんなものをご自分で観に行かれたり、学びに行ったりされたんですね。大学生の時に何か刺激を受けた作品はありますか? 女屋: 高校生の時にピナ・バウシュの「カーネーション」の来日公演を生で観たことがあり、それも印象深いですし、倉田翠さんの「鳴りやまない騒音や終わりのない苛立ちのなかにどれだけしゃべっても伝わらない何かが残った」という作品や、ディミトリス・パパイオアヌーの「THE GREAT TAMER」などは、大学時代に観ていたりしました。個人的にはシアターの要素が強い作品が好みです。 森嶋: 女屋さんはもちろんダンサーとしても活動していらっしゃるとは思いますが、個人的には「振付家としての方がより力を発揮しそうだな」という印象を持ちました。振り付けを始めたのはいつ頃からなんですか? 女屋: 大学1年生の秋です。 森嶋: 今までいくつくらい、作品をつくられているんですか? 女屋: 小さいのも入れると、5~6作品くらいでしょうか。 森嶋: その中で何かご自身の分岐点になった作品はありますか? もちろん最初からいきなり「会心の作品ができたぞ!」というわけではないとは思いますが、徐々に手応えというか、面白くなってきたと思えた作品などは。 女屋: そうですね、大学でやっていた時は、やはりみんなで作品を出したりするので、舞台の転換などの制約もあり、自分自身としてはなんとなく消化不良の感じもあったのですが、横浜ダンスコレクションで賞をいただいた「I‘m not a liar.」というソロ作品は、自分のやりたいことがシンプルに実現できた感覚がありました。素直にやりたいことを出せた作品だと思っています。 そのソロの作品はコロナ期間中につくりました。本当に何もやることがなくなって、ずっと実家にいたのですが、地元のスタジオが場所を貸してくれて、場所と時間だけはあったという状況で、世の中の情勢にも嫌気が差し、「何か理不尽だなぁ」と感じることが多くて…そういうエネルギーが溜まっていたんですよね。あまり良いエネルギーではないかもしれませんが。そういう「言いたいことがあるのに、自分が動けない」みたいな状況の時にソロの作品をつくり、ちょうどその時の環境と自分のエネルギーが一致したような感じでした。 森嶋: 大学はその時は休講ですか? どのくらい失われた時間があったのですか? 女屋: もう全部休講です。1年弱は大学に行っていないですね。大学4年生の4月の卒業公演も中止になってしまい、それから卒業までまともに授業を受けられていないので、大学3年生からそのまま卒業式、という感じです。 森嶋: いちばんの集大成の時に、悔しいですね。 女屋: そうなんです。私たちの代だけ卒業公演ができていないんです。 |
 ぐんまバレエアテリエ2016にて、オーロラ姫第二幕のバリエーションを踊る様子  初めて自分で創った作品を踊る様子。お茶の水女子大学モダンダンス部「An die Tanz」より「シャツのシワ」(2018年、文京シビックホール)photo_TETSUYA HANEDA  初の自作ソロ作品「I’m not a liar.」からの一枚。 横浜ダンスコレクション2021コンペティションII「I’m not a liar.」(2021年、横浜にぎわい座のげシャーレ)photo_大野隆介 |
|
ラストシーンから始まったクリエーション 森嶋: でもそういう逆境を生かして、このような作品をつくられて、そこから今回の「エピセンター」に続いていったんですね。 女屋: はい。この作品は、ソロで新人賞をいただいた翌年の横浜ダンスコレクションで作品を上演できるということで、つくった作品です。 森嶋: ということは、つくりたいという自分の思いが湧き上がった時につくったというよりは、上演の期日が決まっていてつくった作品だと思うのですが、この題材にしようと思われたきっかけはあるのですか? 女屋: 最初は「揺れる」という現象に着目したというか、興味がありました。そこには明確な理由があるわけではなく「面白いな」という感じです。「揺れていながら安定している」みたいな状況が面白いと思って。そのとても小さなテーマから始まって、体の揺れや心情の揺れ、関係性の揺らぎ、境界線の揺らぎ…というふうに広げていって、そこから第二の大きなテーマとして「東日本大震災」を要素として組み込もうという結論に至りました。 森嶋: 重ねていったというか。 女屋: 震災があったのは私が小学校6年生の時。私の地元のスタジオがアウトリーチ活動を頻繁に行っている所で、2014年、震災の約3年後に宮城県にクラシックバレエを踊りに行ったんです。小学校の体育館に舞台を組み立てて作品を上演する機会があったのですが、そのアウトリーチ活動の一環で、現地の人に直接お話を聞いたり、津波で流された町を見たりした経験があります。それが私が高校生くらいの時。その経験がふと蘇ってきて、「あ、あの時聞いた話、今なら作品にできる」と思いました。それは「作品に利用する」ということではなく、自分の中で咀嚼して表現として提示できるタイミングだと思ったということです。動機としては、それが大きいと思います。現地を訪問した当時の私には、自分の力ではその大きすぎる悲劇を扱えない、手をつけられないという感覚だったのですが、ここへきてようやくちゃんと向き合うべきだと思い、作品のテーマに組み込みました。 森嶋: 「揺れる」というのはかなり幅の広い言葉だと思いますし、いろんなものを重ねられると思うのですが、創作過程は最初からわりと順調に進んだのですか? 女屋: いえ、そうではなかったです(笑)。2月に新人賞を受賞して、同年12月に新たな作品を上演するという、その年だけイレギュラーなスケジュールだったので、6月ごろから創作を始めましたが、私はまず、他のダンサーも登場する40分の長い作品をつくること自体が未経験でした。それまで最も長くてソロの10分の作品しかつくったことがなかったので、どこから手をつけていいかさっぱり分からず、最初は本当に困っていたんです。クリエーションの起点として、私はシーンが最初に映像として思い浮かびます。「こういう関係性が見たい」とか「こういう動きや動作が見たい」とか、頭の中に出てきたそういうシーンをまずいろいろ試してみて、そこからどう展開していくのかをダンサーとディスカッションしながらシーンを少しずつ増やしていき、なんとか40分をつくるという感じでした。 創作期間の途中で、横浜の大きなスタジオを集中的に借りられる期間が2~3週間ありました。そこでグッと作品がブラッシュアップされたというか、出来上がりかけていた作品を、一度壊していくような作業に取り掛かっていったんです。そこから上演の1週間ほど前に、海外の方が急に来られないことになり、10分ほど作品の時間を伸ばす必要も出てきて、ダンサーのみんなにたくさん助けていただきました。「こう見える」とか「ここはこう展開していった方がいいんじゃないか?」みたいな意見をいろいろもらって、実験的に試しながらつくっていった感じです。「これが正解」と言える作品ができたかどうかは分かりませんが、「これが今はベストだね」と言えるものをつくりました。
|
 エピセンターを短編に作り直し、再演した際の一枚。コレヲミックス「エピセンター 改編版」(2021年、シアターアルファ東京)photo_大洞博靖 |
|
森嶋: いちばん初めに浮かんでいたシーンや、取っ掛かりとなったシーンはどんなものですか? 一つかもしれませんし、複数かもしれませんが。それは作品が仕上がった段階でも残っていますか? 女屋: 基本的には残っていますね。卒業公演の未練があったのかもしれないですが、伸びるシーツを被って動くというのを卒業公演でやろうとしていたので、どうしてもそれが捨てられなくて、結局それを「エピセンター」でも使うことになりました。輪郭の揺れというか、形が定まらない様子をそれで表現したいと思い、シーツを被って動くというシーンは残っています。そのシーツを被った人の輪郭をガムテープでなぞるというシーンも、わりと初期のアイデアです。他にはキーワードとして、「後悔」とか「言わなければよかったこと」とか「言っておけばよかったこと」。震災でたくさんの人が亡くなっているわけですが、その方々が抱えて亡くなっていった魂とか、その方々たちに向けて生きている人たちが抱えている未練や後悔、そういうものにフォーカスしたいなという思いは最初からあり、作品の中に残っています。ラジオの音もですね。ラジオライトや、バケツ、水…そういう要素は初期の段階から使いたいと思っていました。 森嶋: 小道具の使い方も上手というか、しつこすぎず、道具が前に出過ぎずとてもよかったなと思います。それはご自身のアイデア? 女屋: そうですね、物を使うことは学生時代からけっこう多く、それはおそらくピナ・バウシュのヴッパタール舞踊団の影響だと思います。物の使い方は稽古で決めていった感じで、物を「意味」としてどういう距離感で使うのかとか、物に対しての「意味」の統一性やつながりは言葉でかなりディスカッションしました。「聞きたいけど聞こえない」とか「見たいけど見えない」とか、そういうワードが出ていましたね。小道具を使って30~40分インプロをするということを、集中稽古の時にずっとやりました。物だけを舞台上に置いて、ダンサーが自由に集団即興する時間を長く取り、その時に見えた良い絵とか、物の使い方をピックアップして作品に組み込んだシーンが何ヶ所かあります。 森嶋: すごいですね。想像と違った部分と、想像通りの部分がありました。小さい頃からコンテンポラリーダンスの作品に触れていたというのは納得感がありましたが、あの作品が初めてのグループ作品であるとか、40分の長い作品であるという点には驚いてしまいました(笑)。 最後まで出来上がって、今の時点でお気に入りのシーンや納得のいっているシーンはありますか? 女屋: ラストシーンです。これも最初から見えていたシーンというか、これで終わりたいなと思っていたシーンで、今でもこれで終わってよかったと思っています。一人が死体のように床に倒れていて、バケツから大音量の「ラヴィアンローズ(薔薇色の人生)」が流れ、それに倒れたまま自分の手を被せて音がだんだん小さくなって終わる、というシーンは、自分の中ではわりとしっくり来ています。 森嶋: 早い段階でそこは見えていたんですね。 女屋: あのシーンは決まっていましたね。あれに向かっていくためにどうするか? みたいな感覚はありました。 森嶋: そういう所が振り付けの説得力として表れたのかな。非常に興味深いですね。 女屋: 逆に私はそういうシーンしかつくれなくて、いわゆる「ダンスのシーン」がつくれないんですよ。それが私の今の悩みでもあります。関係性をつくるとか、映画みたいに、演技じゃないですけど動作するシーンは浮かんでくるのですが、ダンスがなかなか振り付けできなくて。でも「もっと踊っている所を見たい」というような、ダンスを見たい観客も大勢いると思いますし、私自身が小さい頃からメソッドとしてテクニックをコンスタントに続けてきたので、踊り自体を見せてほしいというご意見も多々いただくんです。でも私としては、舞台で振り付けを踊るということに無理があると感じてしまう瞬間があって、「エピセンター」をつくった時もずっとそれに悩んでいました。ユニゾンをここでやったら気持ち悪いとか、ここで全員で踊るにはまだ早い、エネルギーが足りないとか、そういうことをずっとやっていたのですが、ここ最近KYOTO CHOREOGRAPHY AWARDに向けたリハーサルを始めて、少し吹っ切れて、「もう踊ってしまえ」という気持ちになってきました(笑)。今は少しずつ振り付けを入れてみているのですが、いまだに自分の中で納得しているシーンは、いわゆる振り付けではないシーンが多いです。バケツを伏せたり、一人立っているダンサーに振り向いて走っていって抱きついたり、「カット割」ではないですが、そういう要素の一つ一つに納得がいっているという状態です。そこから踊りにつなげる所が、まだ改善の余地というか、試行錯誤している感じですね。
|
 新作発表に向けて、横浜の急な坂スタジオで稽古をしている様子 |
|
「共感」ではない。「言葉には表せないような感覚」を突く 森嶋: では他の方の作品を見ていても、例えば「なんでここで踊るんだ?」というか、踊りの必然性を疑う、みたいなこともあったりしますか? 女屋: それは本当によくあります。もっと素直に見れるといいなと思うのですが(笑)。ああユニゾンしちゃったなぁ、みたいに感じたり、きれいに揃いすぎているのが不自然な感じがしたり、私が今扱っているテーマの影響もあると思いますが。でも説得力のある踊りを見たら感動しますし、拒否するわけではないですし、もちろん踊りや振り付けは面白いと思います。一方で、やはりそこに無理があると引いてしまうというか、他の人の作品を見ていてもそう感じます。 森嶋: その辺に女屋さんの魅力があるのかもしれないですね。踊りに対する必然性というか、妥協のない姿勢というか、「なぜダンスなのか?」みたいなことを解いている。そういう所が、僕が感じている「振付家らしさ」なのかな。僕の知るダンサーたちは、踊ることが楽しいからシンプルにスーッとダンスに入れる方が多い中で、女屋さんには作家性というかこだわりがあり、それが作品の中に出ているような気がします。それでいて非常にお若いので、どんどん驚きが増えていったという感じです。おそらくまだ、観客に対して何かを伝えたいというよりは、まずは自分のつくりたい世界をしっかりつくろう、みたいな感じなのかなと思うのですが、何かありますか? 観客に伝えたいこと。 女屋: 作品を通してこういうことを「伝えたい」みたいな意志はあまり無くて、そんなに偉くないというか、みなさんと同じ目線ですし、わざわざ大袈裟に「メッセージとして届けたい!」みたいなことは昔から無いんです。それよりも自分が今描いているイメージや不快感をできるだけ作品に投影した上で、少しでも響くことがあるといいなというか、心の少し弱いところを突かれているような感覚になってほしいという感じです。 今SNSなど「共有」できるものがたくさんあるし、いろんなものに名前がついて形づくられて、どんどん世界が形成されていると思うんですが、その隙間にあるもの、簡単に言ってしまうと「言葉には表せないような感覚」、何か心がえぐられるとか、突かれる、そういうところにアプローチできたらと思います。それがテーマの共有につながると思うし、見た後に考えさせられるというか、何かが残るだろうと思う。 ですからもちろん作品としては完成度が高い方が良いとは思いますが、こちら側で自己完結した状態で作品を上演するというより、余白を残したまま上演できるように心掛けています。見え方が人によって異なるシーンなど、「答え」や「結論」を提示しないように心掛けているので、それが観客に伝わるといいなと思います。
|
 作品「エピセンター」のグラフィック。稽古の様子やコンセプトを共有し、描いていただいた一枚。(グラフィック_りら) |
|
森嶋: 完成度という意味ではなく、「これでおしまい」みたいな状態をつくらないということですね。映画でいう「完」みたいなものをつくらずに、その先も伸びていくような。「共感」というより「共鳴」や「共振」、深い所にある感覚を一時的に共にするというような感じなんですね。 女屋: 「共感」はできない気がします。突拍子も無さすぎて(笑)。作品の中で水風船を口から出して割ったりしているんですが、日常ではあり得ないことですよね。それを見て「共感」はできないと思うのですが、その水を被った人の表情とか、水風船に入っていた水を顔に被せている人の状態から、「あれに見える」とか「こう感じる」とか、そういうことですね。 森嶋: そういう感覚的な所を実際に作品としてつくっていく上で、その振り付けや演出を他の人に対してしていく際に、どんなアプローチで伝えながらつくっているのですか? 女屋: 私の場合は先にイメージというか、映像が出てくるので、まず頭に浮かんだものを私が段取り的に説明します。ダンサーもその時は「???」という状態になるんですけど(笑)。でもとりあえずやってもらって、上手く具現化できることもあれば、できないこともありますが、すんなり行った時はそのままやってもらいます。イメージの話をすることが多いかもしれないです。例えば人の肌を触るシーンでは「液体みたいなものが知らないうちに首元から入って来て…」みたいに。 森嶋: 「こういうふうに見えてほしいから、こんな動きをしてほしい」というよりは、動きそのもの感覚から入っていって「こう見えたらいいな」というつくり方をされている? 女屋: そうですね、「これがこういうふうに見えたい」という指示はあまり出さないかもしれないです。「こういうシーンが見たい」というのが先行して、そこから体でやってみながら議論します。動画を撮ったり、他の人の動きも見たりして、私がイメージしたシーンが実際にやってみてテーマにどうつながるのかとか、どう見えるのかを話し合い、じゃあこうした方がこの作品のこのシーンではしっくりくるんじゃないか、というふうにして変更を加えていきます。 森嶋: では、ボツになったシーンも? 女屋: たくさんあります(笑)。 森嶋: 絵を描いたりしますか? そのみたいシーンの絵コンテみたいな。 女屋: それはしないですね。 森嶋: でも頭の中には絵コンテみたいな映像がある。 女屋: はい、あります。 森嶋: それはある意味で「映画的」というか、どう動くかとか、どういう振り付けにするかというディテールよりも、どういう位置に人が配置されて…という「絵」がありき? 女屋: 振り付けよりも演出にかけている時間の方が長いです。振り付けはわりとパッとつくることが多い。それは私が振り付けが得意ということではなくて、振り付けを考えて踊った上で、その踊りがどう発展していくのかの方が見たいという気持ちがある。振り自体のクォリティももちろん大事ですが、その振り付けがどういう「意味」でできているのかとか、「踊り出す理由」が私にとっては重要なんです。振り付け一つ一つの意味ということではなく、動いている人の動機、心情や関係性の方に時間をかけることの方が多いですね。 森嶋: ポジショニング(舞台上のどこに人や舞台美術、小道具を置くか)だけでもかなり絵が変わってくるじゃないですか。女屋さんの作品はポジショニングがとても良いなと思います。それはやはり頭の中の絵コンテがしっかりできているからでしょうね。シーンの切り替えもけっこう早いというか、いろんなシーンが出て来ますよね。 女屋: そうなんですよね。やはりシーンから先につくっているというか、細かな画像からつくり、それを次々に出していく。基本的に作品にあまりストーリー性は無いので、そのつくったシーンをどうつなげていくかは毎回すごく悩みます。そのシーンに行けると思ったけど無理だった、みたいなこともあります。ポジショニングで言うと、4人はけっこう難しいなと今も思っています。1:3だと1に意味が出過ぎるし、2:2だと平板になってしまうし。そこは今も難しいなと思ってはいるのですが。 森嶋: 人を増やすか、減らすか、どちらのタイプですか? 女屋: 増やしたいですね(笑)。なかなか大人数でやるとなると、現実的に予算も大変だったりしますが、今は大人数でやりたいなと思います。 森嶋: 人数が多い方が、女屋さんの「絵コンテ力」がさらに生きるのかなと思いました(笑)。でもまさにこれからですからね、キャリアは。今回応募したきっかけは何かあるんですか? 女屋: 実は去年に一度出しているんです。コロナ期間中に「悔しいから何かつくって出そう!」みたいな意気込みだけで、学校の古いダンス室の映像で送ったという経験があります。ですからイベント自体は存じ上げていて。「2022年度も開催します」というメールを見て、長さがちょうど良さそうな作品を上演したばかりでタイミングよく手元に持っていたので応募しました。それと、やはりディスカッションの時間があるというのがすごく貴重だなと思ったので。普通は上演して終わりで、後でTwitterで名前を探したりして反響を知るという感じなので、実際に振付家の方々とちゃんとディスカッションできるのは貴重な機会ですし、単純に面白そうだと思いました。みなさんのお話も聞きたいですし、それが応募の動機として大きいですね。
|
 「エピセンター」photo: Ohno Ryusuke  「エピセンター」photo: Ohno Ryusuke |
|
ダンスの必然性を疑うことさえできる。「答え」がない魅力 森嶋: そろそろ最後の質問になりますが、女屋さんはコンテンポラリーダンスが好きですか? どんな所が魅力でしょう? 女屋: いわゆる「コンテンポラリーダンス」と呼ばれているジャンルは好きです。自分のやりたいように空間や人や身体を自由に使えるのは大きな魅力です。声や道具を使ったり、床を汚したり、そういう自由度の高さや解釈の広さみたいなものに、非常に可能性があると思います。例えば演劇やミュージカルはストーリーやセリフがあるからこそ意味が限定され、もちろんそれは分かりやすいし、ストーリーが面白いという面もあります。一方で、観客は人それぞれ背景が違います。コンテンポラリーダンスの舞台においては、私は「受け取り方の違いの面白さ」がすごく楽しい。自分自身がやっていてもそこが面白いし、見ていても面白い。見方を制限せず、観客に委ねられている所に魅力を感じます。 また、シンプルにテクニックとして身体が動くのはやはり面白いですね。自分がダンサーをしているからかもしれませんが、「身体の中に生まれている世界観」みたいなことがとても神秘的だと思いますし、その人のパッションが見えやすいと感じます。私はクラシックバレエを長年やっていて、厳然と「これが正解、これはNG」というものを教えられて来たので、何か「湧き上がるエネルギー」とか、逆に「抑える」とか、身体の中と外にあるエネルギーのやり取りを感じながら表現できるのは、コンテンポラリーダンスのとても素敵な部分だと思います。 森嶋: 「ダンスの必然性を疑う行為」って、ダンスからはみ出しているような気もしますが、でもそういう表現も許される。それがコンテンポラリーダンスであるという、なんだかテレビのまとめ方みたいになっちゃいますが(笑)、僕はその女屋さんのはみ出し方がユニークだと思いますし、今後ダンスに一通り満足したら、また違う表現にも取り組んでいくかもしれないなと思いました。例えば言葉を喋らない演劇とか、映像の世界とか、いろいろな所に飛んで行けそうだなと感じました。 女屋さんが今後、振付家やダンサーとして表現活動をしていく上での展望を聞かせていただけますか? 女屋: 私が作品をつくる上で、映像や画像、シーンが先に出てくるという話をしましたが、それを理論的に裏付ける知識が足りていないというか、最近ようやくそこに興味が出て来たんです。シーンが頭に浮かんでくるからこそ、それを理論や知識で裏付けできたら強さが出るんじゃないかと思い、美学や哲学などの知識をもう少し取り入れたいと思っています。学生時代は終わったのに、今ようやくそこに興味が出て来て(笑)。実際にそういう所から得るものも多く、理論の勉強をもう少ししたいと思っています。 ダンスしかやりたくないということではなく、文章を書くことや、プロットをつくることにも興味があります。自分の表現している世界観を、どういう方法を使って裏付けていったらいいのかを探っていきたい。同時に、やはり自分自身がダンサーでもあるので、踊る身体をいかに作品に組み込んでいくか、いかに違和感なく踊る身体に持っていけるかということは、今回のKCAはもちろんですが、今後も向き合っていきたいテーマです。 森嶋: 24歳で、もうご自身の課題も見えているんですね。まさに伸び盛りの時期ですね。さらに期待がふくらみました。
|
 彫刻家やタップダンサーなど、様々な肩書きを持つ6名での即興パフォーマンスでの一枚。 Conceptual Session Live「浮漂」(2022年、Double Tall – Art & Espresso Bar)photo_田中洋二 |
|
振付家 女屋 理音(オナヤリオン) 作品概要「エピセンター」 インタビュアー 森嶋拓(モリシマヒロシ)
|
|
|
「KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2022ー若手振付家によるダンス公演&作品を巡るディスカッションー」 Interview |