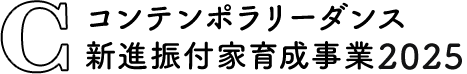KCA2022振付家インタビュー② 池ヶ谷奏、藤村港平
僕らを踊りに駆り立てる、「対象a」とは何か?
掲載日:2022/12/28
聞き手:林慶一(制作者)

|
ダンサーとしての二人のルーツ
林: 初めにお二人のこれまでの取り組みや現在の活動について教えてください。 池ヶ谷: 私はダンサーとして活動しています。約10年間「Noism」という、新潟にあるダンスカンパニーに所属していて、そこがプロダンサーとしては最初の場所です。2年前にフリーランスになってからは、いろいろな振付家の作品に関わらせていただいており、日頃はつくるより踊る方が多いです。新潟と東京の2拠点で活動しており、指導者としてもバレエとコンテンポラリーダンスを教えています。バレエ教室での振り付けや、自分自身での作品づくり・発表も行なっています。 林: コンテンポラリーダンスはNoismに入る前からやっていたんですか。 池ヶ谷: 習い事ベースですが、子どもの頃からクラシックバレエとコンテンポラリーダンスも踊っていて、発表会やコンクールに出ていました。お茶の水女子大学の舞踊学科に進み、創作の方法やダンスにまつわることを学んで、そこで初めて「自分で作品をつくる」ということに触れました。 林: バレエと共に、コンテンポラリーダンスにも若い頃から触れていたんですね。ご自身の活動としては、今はもうコンテンポラリーダンスに軸足を置いて取り組んでいるんですか。 池ヶ谷: そうですね、今はダンサーとしてバレエの発表はしないです。自分のトレーニングのためにトウシューズを履いたり、指導者としてはクラシックバレエのクラスも持っています。 林: 藤村さんはいかがですか。 藤村: 僕もダンサーとして活動しています。「振付家」と名乗ったことはあまりないです。肩書きとしては「舞踊家」という言い方をしていますが、基本的にはダンサーを生業にしています。大学時代に舞踊美学といわれる領域で研究をしていました。ダンスについて研究する過程で自分の中に湧いてくるいろいろな疑問や問題を解決するための手段として、作品をつくったりもしています。だから振付家とも言えるし、ダンサーとも言えるかもしれません。でも自分の行為が「振り付け」だとは思っていないです。何かをつくってはいるけれど、それは振付家という肩書きじゃなくてもいいし、ダンサーの身体でも何かをつくることはできるので。 林: 舞踊美学はどちらの大学で学ばれて研究していたのですか。 藤村: 筑波大学です。実は筑波大学に舞踊美学専攻の学科があったわけではないんです。自分で興味を持ったので独自に研究していました。他の大学の専門の先生に指導してもらったりなど。 林: 筑波大学だと平山素子さんが教えておられますね。 藤村: そうですね、僕の大学の恩師です。 林: では舞踊美学は独学というか、藤村さん個人の関心を拠り所にして取り組まれたんですね。 藤村: そうです。修士論文の執筆時にはどうしても舞踊美学の分野で書きたいという思いがあり、研究室の先生に無理を言いながら研究を進めました。 林: 池ヶ谷さんも作品の創作は以前からされていたんですか? 池ヶ谷: はい。大学で創作を始めて、発表としては小さいものばかりですが。新潟でも自分で創作したり、他ジャンルのアーティストと共作して上演しています。 |
 ©︎Noism『NINA―物質化する生け贄』演出振付:金森穣 撮影:篠山紀信  Noism時代(池ヶ谷)Photo:遠藤龍  藤村個人での活動『FUTOMANI』Photo:bozzo |
|
コンテンポラリーダンスの捉え方 林: 「コンテンポラリーダンス」は舞踊分野として一括りに捉え難く、やっている当人たちでさえ説明できないことが多いですね。。そこで、お二人は「コンテンポラリーダンス」をどのように捉えて関わっているのか、もしくはコンテンポラリーダンスということは特に意識していないのか、その辺りの考えを聞かせてください。 藤村: コンテンポラリーダンスは一つのジャンルのような扱いをされますが、それは20世紀末から始まったムーブメントとしてそう呼ばれていたに過ぎないですよね。なので今「コンテンポラリーダンス」なんて言っていたら、まずいんじゃないかって。僕は自分自身のダンスを「コンテンポラリーダンス」とは何としても呼ばない。未だにそう呼んでいることがかえって同時代的でないという危惧から、僕は自分のダンスがコンテンポラリーダンスだとは意識していないです。 林: すると、藤村さんは何に軸足を置き、どんなスタンスで表現に取り組んでいるのでしょうか。 藤村: 例えば音楽に比べると、ダンスはどうしても歴史的な弁証法が薄い分野だと思います。理論を積み上げていくという発想があまり無く、常にガラパゴス的に突拍子もなく新しいものが生まれる、みたいなことが多いし、特に日本はそうなりがちだとも思います。そういう文化圏や時代性だからこそ、歴史の産物を踏まえてダンスをつくっていけたら、踊っていけたら、とは思っています。 ただ、そうは言っても真面目な顔して稽古場に通っているだけでは、歴史を解釈することすらできないので、他分野とのクロスポイントみたいなものも意識はしていて、僕の場合は哲学や形而上学が常に頭の片隅にあり、そういう視点を利用して踊りに関わっている所があります。やっている事は同じようなことでも、「身体に対峙する際の視点や思考をシフトすることで新しい問いを見つける」ということを大事にしています。 林: 「ダンスの歴史を踏まえて」という話がありました。藤村さんの言うように、日本のコンテンポラリーダンスはまさに「ガラパゴス的」で、興隆期にはそのガラパゴス性が、欧米のダンスに対して良い意味でのコントラストを示していたと思います。しかし、それ故にシーンとしての動向や実績が蓄積されるシステムが成り立たなかった。出来事が線で結ばれず、さまざまな断片が伝説的に語り継がれる日本のコンテンポラリーダンスが表現としての「歴史」を語ろうとするとき、それは欧米圏のダンスの歴史を代弁するような形になりますね。 藤村: 今の日本のダンスの複雑さは、「ガラパゴス的」である一方で欧米からの影響も無頓着に受けている点にある気がします。もし、「日本のダンスも西洋から始まるパフォーミングアーツの歴史の延長線上にある」と仮定しそれを認めるならば、一度その始点、中心地に戻り、そこから改めて脱中心化を図るのも良い気がします。少なくとも僕のバックボーンは明らかに西洋のダンス、西洋の音楽、西洋の哲学にあるので、そういう姿勢にならざるをえないというのはあります。コンテンポラリーダンスを始めたのは15〜16歳の頃ですが、コンテンポラリーダンスを始めてすぐにクラシックバレエも習い始めたんです。なぜか昔から僕の物事に取り組むマインドとして、古典まで遡って学び始めるというものがありました。「哲学ならソクラテスだし、音楽なら多分バッハ、ダンスを本格的にやるならまずはクラシックバレエからだ」みたいな。そういう意味ではその後の流れにあるダンスも可能な限りは体験するし、文献もとことん漁り、知識も身体知も蓄積した上で、「今、何ができるか」を考えようとします。 こうしたアプローチはダンスでは難しい部分もあります。音楽は歴史の勉強がしやすくて、例えば「バロック時代はこういう理論でこういう響き方」などということは、300年近く経った今でも楽譜や理論書を読めば理解できるし、自分でピアノを弾いてみれば歴史を体験できる。それに対してダンスは、どうしても失われていくものが多いので難しいのですが、可能な限り拾い集めます。
|
 藤村個人での活動『FUTOMANI』Photo:bozzo |
|
林: 池ヶ谷さんにも同じ質問を投げてみたいと思います。「コンテンポラリーダンス」をどのように捉えて自身の活動に取り組んでいるのか。 池ヶ谷: 私はクラシックバレエからダンスに入り、コンテンポラリーダンスと呼ばれる作品を小学生の時に見て、古典よりもかなり幅の広い表現方法があるという、そこの衝撃が大きかった。「バレリーナよりコンテやりたい!」と幼いながらに思いました。でもクラシックバレエをやっていた土台があるからこそ、コンテンポラリーダンスの表現の幅広さを生かせると捉えています。ですから、「何でもあり」という、とても自由な表現でコンテンポラリーダンサーを名乗っている人が増えている印象がありますが、私は基礎やトレーニングは大事にしたい。そういう意味では一昔前の「コンテンポラリーダンス」と呼ばれていた時代の方が、私には合っているのかもしれません。今は誰でも「ダンサーです」と言えてしまいますが、私は「何でもあり」ではなく「決まりのあるもの」が好きなので。 林: 「決まりのあるもの」とは? 池ヶ谷: 簡単に言うと、ポジションや、腕と足との関係性、体幹の使い方、単純に気持ちいいというフィーリングだけで表現しないこと。そこに何か制限をかけることで生まれる新しい体の見え方を重要視している。「決まり」というのは、「制限」ということですかね。 藤村: 僕はコンテンポラリーダンスにも決まり事はあると思います。自由に踊るとか、何でもありなのがコンテンポラリーダンスだと思われているけれど、そうではなく、何をやってもいい自由な所で、ダンスクラシックに匹敵しうる理念を同時代の視点から組み立てて実践していくのがコンテンポラリーダンスだと僕は思う。僕からしたら全然何でもありではない。それは「芸術」ではないだろうとすら思います。 そういう点で、僕は何か池ヶ谷さんとシンパシーというか、近しいものを感じて一緒にやってみようと思ったんです。コンテンポラリーダンスは世の中で言われているほど自由なものではない。「何でもいい・何でもあり」な所には芸術の歓喜はありません。「規定の価値や概念を批判し問いを見出すことからしか創造的な行為は始まらない」というのが、僕の考え方です。 林: そこでお二人の接点が見出せたんですね。一緒に取り組みを始めたのは具体的にどんな経緯だったんですか? 藤村: 2年ほど前に、Dance Base Yokohamaで鈴木竜さんが新作をつくるということでトライアウトのクリエーションをする機会があり、そこで池ヶ谷さんと知り合いました。僕と池ヶ谷さんと鈴木さんの三人で踊る作品ですが、少し特殊なクリエーション環境で。“コレクティブ”という考え方の下、ドラマトゥルクの方や美術の方、音楽の方などかなり多様なメンバーがフラットな状態で創作を始めるという場でした。だからお互いの価値観も短い期間でわりと理解できました。 最初は池ヶ谷さんから声を掛けてくれたのですが、それは「一緒にものづくりをしよう」というよりも、「新潟でリーズナブルに借りられる小屋があって、何か作品を一緒に踊りたいんだけど…」という感じだったんです。それで「じゃあ僕、ちょうどつくりたいものがあるし、一緒にやろう」となって始まりました。 池ヶ谷: 新潟に藤村さんを呼んだんです。 林: それが今回応募した作品ですか? 藤村: いえ、一つ前ですね。 池ヶ谷: 2021年の3月に発表した「instant scorer」という作品です。 林: なるほど、お二人で作品をつくるのは今回で2作品目なんですね。
|
 池ヶ谷個人での活動 Photo:Kenta Yamaji  池ヶ谷個人での活動 |
|
踊りはいつ始まっている? 「ダンスする身体」に生まれ変わる時 林: 前回の作品と今回の作品とでは、コンセプトや取り組みの軸は変わらないんですか? 藤村: 根本は変わらないですね。というのも、コンセプトに掲げているような部分は、僕が大学生の頃からずっと取り組んでいることなので。 林: では応募作品の話に入っていきましょう。「対象a(アー)」という作品について教えてください。 藤村: 僕がずっと興味があるのは、「ダンスになる瞬間って、いったいいつだったんだろう?」ということです。「踊る」とは言っても、動いたらダンスなのかというと、そういうわけでもない。振り付けをもらっても一向にダンスが始まらない時もある。でも舞台に上がって、気がつくとダンスになっているという瞬間もある。日常の身体が全く別の「ダンスする身体」に生まれ変わっている時があって、それが切り替わるのはいったい何によってなんだろう? という問いが 僕の中に長くあります。それが「身体はいかにして舞踊する身体として再構築されるのか?」という問いです。 それを追求するための一つの切り口として、ジャック・ラカンという、精神分析や哲学を行っていたフランスの思想家の理論を援用することで、何か近づけるんじゃないかという試みがこの作品「対象a」です。 林: 「シニフィアン」という現代思想の概念をキーワードに据えておられるようですが、これがどのような事を意味しているのか教えてもらえますか。 藤村: おそらく「唯名論」的な考え方が根底にあります。世界というのは漠然としたカオスの広がりで、そこで人が物に名前を与えていく、つまりカオスに名前を与えていくから、我々は一つ一つを分化して認識していくことができるという考え方です。例えば今、僕の目の前にはカオスが広がっているけれど、「パソコン」、「コーヒーカップ」というふうに名前を与えるから、それらがカオスから分化して、一つの物として認識できる。ラカンの場合はそれを「シニフィアン」と呼んでいるんです。この「シニフィアン=世界を切り裂いていく」という考え方がダンスでも援用できるのではないかと。要はダンスも「ダンス」という漠然とした概念だけれど、僕らはダンサーに固有のシニフィアンを用いて「ダンス」や「身体」という漠然としたカオスを分化し、アクチュアルなものにしていくことができる。それがきっかけの出来事となって「舞踊する身体」が立ち現れるのではないか? と。 そして、一つのシニフィアンによって、ダンス、あるいは身体というものを切り裂き分化する時に、次々に、何か、「もっとこうしてみたい」という志向性が芽生えてくる。それを僕らは「対象a」と呼んでいる。つまり、シニフィアンによってカオスを切り裂いた時に余る余剰が「対象a」で、それが僕らを踊りに駆り立てる。 池ヶ谷: 一緒に作品をつくる時は、藤村さんに勉強会から始めてもらい、今のような難しい単語が出てきたら、言葉の後に一緒に動いていてみて、「ああ、こういうことか」と私なりに解釈をして…二人でただ立っている状態から、最初の動きはどこから生まれるんだろう? と問いながら、ほんの少し瞬きしたことで下に下がるとか、こうしたらこうしたくなるよね、みたいに「次が生まれる瞬間」と「生まれた動き」をどんどんキャッチしていくという作業を繰り返していきました。そういうふうに実践することで、私も哲学的な難しい言葉を自分の中に入れていったという感じです。 林: もともと宇宙や世界は混沌そのもの、何でもないものだったのが、シニフィアンによっていくつもの要素に「切り裂かれ」ていくことで、私たちの認識できる世界みたいなものが立ち上がってくる。そういう哲学的なものの捉え方を作品やダンスにしてみようとする試み、ということでしょうか。ではダンスとして具象化するにあたり具体的にはどのようなことをするのでしょうか。 藤村: まず「シニフィアンによって世界を切り裂いていく」という構造をダンスに援用する時、「ダンスという特別な時空間におけるシニフィアンは何か」という問いが生まれます。そしてダンスの時空間には、身振りや眼差し、呼吸、場合によっては言葉等がダンサーの扱う特異な記号として存在しています。それらがダンスの「シニフィアン」であり、その固有のシニフィアンによってダンスを切り分けていく。 例えば舞台上にダンサーが二人立っていて、何か振り付けがあるわけでもないんだけど、お互いの目がふっと合った、その時のお互いの距離みたいなものを意識して、もう少し近づこうかなと思う。少し近づいたら、それがきっかけで今度は相手がそれとなく動かした右腕が気になり、互いの手を取り合ってみたり…というふうに、一つ一つのそれと意識されない微細なシニフィアンが次のシニフィアンに連鎖していくということが起きます。ところが、これは世界を対象化するのと同じように「切り分けきれないもの」が残る。例えば昨日、とても美しい風景を見たとして、それを人に説明をしようとすると、語れば語るほど「語り尽くせなさ」みたいなものを感じることがある。言語化すればするほど、僕が実際に見た風景とは隔たってしまう。でも喋れば喋るほど、もっと喋りたくなる。もっと「あんな所が、こんな所が」と。 ダンスも同じで、動けば動くほど、ダンスの語り尽くせなさ、拾い切れない「何か」を感じるから踊り続ける。ダンスについては語り得ないけれど、その過程で自分がどこに向かっていきたいのか、みたいな所はどんどん鮮明になっていく。僕が最初に言った「舞踊する身体」という新たな主体がまさに純粋なかたちをもって立ち現れる瞬間なんじゃないかと。つまり踊ることで「私」というものが立ち上がっていく。何かのテーマを表現するための身体ではなく、身体そのものが表出していく。そうなったらいいなと思って踊っています。 池ヶ谷: つくり方としては二人の間で些細な日常の動きをやってみたら次がこうなった、というプロセスでダンスが生まれていくのですが、クリエーションする中で「結局、踊っているように見えるよね」とか、「踊りすぎているよね」と感じて、動きをだいぶ削ったりもしました。 林: 「踊りすぎている」というのは? 池ヶ谷: 動きすぎていたり、日常の仕草だけを取っているはずなのに、やけにダンサブルというか「いかにもダンサーが立っている」というふうに見えたりするということです。それに気づいて動きをシンプルに戻したりしました。そんな発見をしながらつくったのが最初です。 藤村: 多分「踊る」という行為が無頓着に前提されることに対する抵抗みたいなものが働いています。僕らにとっては「記号化していく」、つまり身振り等のシニフィアンでダンスを切り分けた後に、「何か足りない」と感じるもの=「対象a」を感じ取ることが大事だった。足りないから次へ行こうと思う。 しかし、肉体的に訓練されたダンサーというのは、どうしても動きがシームレスで、滑らかで、無駄なく洗練され…、というように経験や習慣により自動化されただけの無頓着な身体知が発動しやすい。そこから脱却するにはどうしたらいいんだろう? という困難さを、お互いに感じている。それがおそらく池ヶ谷さんが言った「踊っちゃってるね」という感じにつながるのではないかと思います。
|
『instant scorer』1 Photo:fukukoiiyama  『instant scorer』2 Photo:fukukoiiyama  『instant scorer』3 Photo:fukukoiiyama  『対象a』Photo:yoshitaka |
|
観客に感じてもらいたいもの 林: 少し視点を変えて、お二人がこの「対象a」で取り組んでいる実験を「観客に見せる」ことについて、どのように考えているのか教えてください。 藤村: 正直な話をすると、僕は自分の個人的な興味が先行しています。それが良いことだとも、許されることだとも全く思っていません。やはりものづくりをして上演するとなったら、観客が何を感じるか、何を感じ取ってほしいかということは、コントロールできないにしても持つ必要はあると思うんです。しかし個人的には今のところ観客に何を感じてほしいか、察知してほしいかはあまり明確になっていないかもしれません。 ただ、観客が必要ないかと言ったらそうではなく、僕もパフォーミングアーツという歴史の上に立っているアーティストの一人なので、観客と一緒につくっていくという感覚はあるんです。人が見ている「眼差し」がないと作品が成立しないという感覚はあります。 池ヶ谷: でも、そう言って邁進してくれる藤村さんを、私が「いや、お客さんいるからさぁ」と客席の方にグイッと向けることもあったりして(笑)、バランスが良いのかもしれません。私は単純に舞台で踊るのが好きですし、見に行くのも好きですが、やはり舞台では日常ではない空間を体感したいし、私が踊る時にも観客にはそういう体験をしてほしいと思います。だから何でもOKでやりたいことだけやっているような表現に対して、「それ、舞台でやる必要あるのかな?」と思うのかもしれません。 今回の作品でも日常の仕草がたくさん出てくるので、踊りに携わっていない人であっても身に覚えのある感覚に通じる面白さを感じていただけると思います。例えばものすごく長時間人と見つめ合うとか、誰でもできるけど日常ではしない。足を上げて回って…というような「いかにもダンサー的」ではない動きの中に自分と共通するものを見ながら、気づいたら急に舞台上の二人が激しく踊っていた、というようなギャップに驚きや面白さを感じていただけるのではないかと思っています。 林: この作品の初演は、旧第四銀行住吉町支店という、劇場ではない場所を会場にしていますね。 池ヶ谷: 新潟にある、国の有形文化財になっている建物で、元々は銀行だった建物です。移築復元されたのですが、昔ながらのカウンターや鉄製の窓口が残っています。元来は踊るスペースではなくレストランで、テーブルや椅子がたくさん置いてあり、見学もできる施設になっていました。そのレストランが閉店し、次のテナントが入るまでの間、この空間を貸し出していたんです。広さも良いし、音の反響も、劇場よりも良いのではないかと思うほどの環境だったので、市に申請して使わせていただきました。音楽のコンサートや写真撮影の場所としてはよく使われていたのですが、観客を入れてダンスを上演することは初めてだったようです。 林: そのようなお話を聞くと、「その場所でどう見えるか」ということ、つまり演出面も非常に気にされていたのではないかと思いますが、いかがですか? 藤村: 最終的には演出的にするのですが、きっかけが何かと言えば、演出が先ではないんです。シンプルに言うと予算やキャパシティを考慮した上で「僕らが使える場所だったから」。ただ、「めぐり会い」みたいなものは大事だと思っています。予算が限られていて、この地域ではここしかないという状況自体が作品の一つの要素になっていく。「偶然性」って大事だなと思います。
|
 対象a フライヤー  対象a 資料 |
|
自らの身体が持つ可能性に出会い続けるために踊る 林: 本作のような実験的な試みを観客に見せることについて考えを伺いましたが、さらにもうひとつ踏み込んで、お二人はそもそも、「なぜこんなことをしているか」についてお聞きしてもいいですか? 藤村: それは「なぜ踊っているのか?」ということですか? 林: 「踊り」という営みのレベルまで掘り下げてもいいですし、今回の作品についてでも構いません。 藤村: 「新しい喜び」みたいなものなのかなぁ。例えば「身体」というものが一つの「宇宙」だとすると、その宇宙について認識可能な範囲を増やしていける。それは自分で作品をつくっていても、人の作品を踊っていても、めぐり会うことですが。そこでは「あ、身体ってこんな視点で見ることができるのか。こういう領域もあるのか」みたいな発見と問いが、どこまで行っても果てしなく見つかる。その志向性こそが自分にとってアクチュアルな喜びであるということかもしれないです。 林: なるほど、身体を宇宙と見立てて。池ヶ谷さんはいかがですか? 池ヶ谷: 私は、踊りの順番が確固として決まっていてテクニックも含め決まり事がとても多いクラシックバレエに対して、「自分で決まりを選択して踊るコンテンポラリーダンス」というものがやりたくて取り組んでいます。私は人と関わるのが好きなので、自分の個性や強み・弱みを知った上で他のダンサーと組んで踊ると、自分を変えてくれたり、新しい発想や発見をさせてくれたりするのが面白いと感じます。ダンサーに限らず、ダンスに関わる全てのジャンルのアーティストとの出会いも含め、新しい自分の身体への発見が得られる世界だと思っているので、それで踊りをやめられない。だから、「出会いたいから」ということですかね。
|
|
|
振付家とダンサーの境界線の行方 林: では、お二人が今後どんなふうにダンスや今の活動を展開させていこうと考えているのか聞かせてください。 藤村: 僕はダンサーとしてやっていこうと思っています。振付家ではないなと。でも、活動を続ければ続けるほど、自分がつくりたいな、つくらなきゃなというふうに考えが動いている。ただ、自分の稼業が「振付家」だとは思っていないんですよ。作品はつくるけれど、それは「振り付け」ってことじゃない。良い肩書が見つからないので「舞踊家」と少し曖昧にして、踊ったりつくったりしている感じです。 林: 藤村さんがおっしゃっていた、「ダンサーの身体でも何かをつくることはできる」ということについて、もう少しその含みを教えてください。 藤村: 例えばどんなアートもそうですが、社会性や政治性が問われたり、そういうものとの関係性において芸術を発表したりすることがよくあると思います。でも一方では「純粋芸術」と言ったらいいのか、「原理主義」と言ったらいいのか分かりませんが、純粋にその領域の美学を突き詰めるという方法もあるわけです。そういう意味ではダンサーは確かに「社会とは、政治とは」という枠組みとアートとの関係を最初から一挙に引き受けることは不得手かもしれませんが、「身体」や「ダンスという文化」について純粋に考えるという視点では、ダンサーもつくることができる。また、そこから社会性や政治性といったものが純粋に浮かび上がってくることもあると思っています。 なぜそういうふうに思うかというと、いわゆる「振付家」というものの在り方が年々変わって来ていることも影響しています。19〜20世紀においては「振り付け」を「ダンサーに渡す」ことで作品をつくっていました。昨今は振付家が「キュレーター的な」と表現されることもあるように、確かに振付家ないしは作家が全体を統括するけれど、クリエイティビティについては、ダンサーも、美術家も、音楽家も作品に関わるみんなが発揮しています。つまり、創造的な部分を担うのが作家だけではなくなりつつある。ダンサーが創造することの領域が大きくなってきています。実際に僕がダンサーとして活動していてもそれはとても感じていて、もちろん古典的に振り付けが決まっており、振付家の理念を完璧に踊り切るというのもダンサーの役割ですが、それよりも僕個人がどんな身体言語を持っていて、どうすれば振付家と共に新しい着地点を見出せるのかということが問われているような気がしています。 そういう意味で言うと、「あれ? 僕がけっこうダンスをつくってるな」と、人の作品に出ていても感じることがありますし、「じゃあ、自分がつくってもいいんじゃないか」と思うんです。 林: 「振り付け」され、それを舞台上で再現する中でも、「ダンスを自らつくる」作業ができるということですか? 藤村: 僕は、フォーマットはわりと何でもいいというタイプです。自分がつくったフォーマットでも、作家がつくったフォーマットでも、いずれにしてもダンサーとしての「問い」みたいなものは作品に表出してくると思うので、そこに向かえるのであれば、誰がつくったフォーマットなのかはあまり気にしていないんです。気にしていないからこそ、自分で立てた問いに対して作品づくりをしているんじゃないかと思います。 林: コンテンポラリーダンスはどちらかというと、「踊り手を見る」よりも「作品を見る」という傾向があると思います。日本舞踊などは確実に「踊り手」を見ますよね、作品はみんな既に知っているから。お二人の取り組みは、「“ダンサー”だと自分自身を認識しながら、二人でつくっている」という所がオリジナリティというか、極めて重要なポイントではないかと思いながらお話を聞いていました。 池ヶ谷さんは、今後の活動の展望についていかがですか? 池ヶ谷: 私はやはり「発見」、「身体が人と出会うことで変わる」ということをこれからもやっていきたい。Noismに所属していた期間が長かったので、今は自分自身を通して、実験しながらいろいろな動きに出会い、見極めている感じです。同じ振り付けを踊ってもダンサーによって見え方が全く違いますから、私が踊ることでどのように見えるのか、別の人が踊ったらどう影響を受けるのか、そういう所がダンスの面白さであり、「私が踊る意味」みたいな所を感じます。 今後もいろんな振付家と出会いたいし、一緒に踊る人が変われば、やはり自分の踊り方や、クリエーションの中で自分が提案することも変わってくる。それは別のジャンルのアーティストとの出会いでもそう。自分がどこまで許容できて、どこまでは自分の個性として揺るぎなくやっていくのか。今は自分の許容範囲を柔軟に探れる時期なので、いろんな出会いをしたいという気持ちがあります。 林: さまざまな出会いに、自分がどのように反応していくのかを見ていきたいということでしょうか。 池ヶ谷: そうですね。他の振付家の作品においても、藤村さんがおっしゃったように、ダンサーから発信してそれが作品に取り込まれる要素はたくさんあります。「振付家」「ダンサー」と定義せず、みんなで作品に向かっている。クリエーションは「ダンス室・リハ室」ではない場所で生まれていることもたくさんあって、一緒に話していたり、ごはんを食べていたりする時に「今の!」、「それ、明日やってみよう!」みたいな、そういう瞬間につくっていることがけっこうあります。 林: お二人の作品の中でもそういうものがたくさんあるんですか? 池ヶ谷: そうですね。藤村さんとは、半年間ずっとクリエーションに一緒に取り組んでいたので、お互いがどんな考え方で踊っているのか分かり合えたし、好みなども近いと分かった。そこからすでに私たちのクリエーションは始まっていたのかもしれません。その線引きは無いように思います。新潟でのクリエーションでも、練習室に向かう車の中で藤村さんが踊っていたり、日常なのかダンスなのかという境目の無い、そういう所でアイデアが生まれたりしている。「今から振り付けの時間」みたいにクリエーションの場が区切られていないのと同様に、振付家だから、ダンサーだからという立場も線引きする必要はないのかなと私は感じています。 林: 日常の所作を作品の中に取り込んでいるというお話を伺いましたが、クリエーションの切れ目も非常に曖昧なわけですね。 藤村: でも、みんなそうなんじゃないでしょうか。いわゆるダンス作品をつくることに関して。稽古場に入ってから始める人って、いないんじゃないかな。 林: お二人の場合は日常的に時間をかなり共有してして、その日常でもってクリエーションしていったということですよね。 藤村: そうですね、新潟では池ヶ谷さんの家に泊まり込んでつくっていたので。四六時中一緒にいて、僕は四六時中、本を読みながら訳の分からないことをずっと呟いていて…という感じだったから、クリエーションは確かに24時間ずっと続いていたのかもしれない。 最後に、僕が先ほどちゃんと答えられなかった、「観客に何を見てほしいのか」という質問に答えておきたいです。 観客にも感じ取ってほしいこと、それは僕らが、踊りの中で「身体という自分の宇宙」を広げていくこと、知らない場所に自分たち自身を運んでいくという営みの痕跡だと思うんですね。例えば、宇宙がどこにあるかと考えると、現代人は皆、基本的には宇宙を外部に求めるわけです。SNSとグローバリズムのおかげで毎日外の世界へと宇宙を垣間見ることに忙しい。でもよく考えれば、身体には、個別に自分にしかない宇宙が広がっている。そういう、作品からしたら前意味的とも呼べるものが感じてほしい部分かなと思いました。僕自身もそれを志向しているし、その痕跡を見る人にも感じ取ってもらえたらいいなと。 (2022/11/16 zoomにて) |
 「対象a」新潟公演 photo: yoshitaka  photo: tatsuki amano |
|
振付家 池ヶ谷奏(イケガヤカナ)、藤村港平(フジムラコウヘイ) 作品概要「対象a 」 我々の身体が、言語やモノ、眼差し、身振り等のあらゆるシニフィアンによって分断される時、その裂け目に残る”我々を駆り立てる、言い表せないもの”を「対象a」と捉え、それが如何にして身体を”舞踊する身体”として 再構築していくのかを考察する。成りつつあると同時に、手の施しようもなく存在する事をやめてゆくという舞踊の本質的な性格は、「私」という人間存在の本質の次元を、我々の眼差しの一歩先へと永遠に葬り去る。
インタビュアー 林慶一(ハヤシケイイチ) 制作者。2006年よりdie pratzeにスタッフとして参加し2005~2015年は自身のパフォーマンス活動を併行して行う。2007年~2021年「ダンスがみたい!」実行委員会での企画・制作。2012年よりd-倉庫制作。アーツカウンシル東京 平成29年度アーツアカデミー事業調査研究員(舞踊分野)。2019年~2021年「放課後ダイバーシティ・ダンス」プロデューサー。2022年、アーツカウンシル東京「未来の踊りのためのプログラム」企画・制作。2022年からフリーランスに転向し主にダンス公演の制作に携わる。
|
|
|
「KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2022ー若手振付家によるダンス公演&作品を巡るディスカッションー」 Interview |