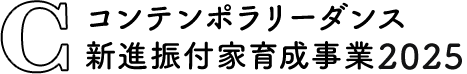KCA2022振付家インタビュー④岡田玲奈、黒田勇
テクニックの引き出しを閉めて、「狼狽」に向き合い直す
掲載日:2022/12/29
聞き手:浅井信好(ダンスハウス黄金4422・月灯りの移動劇場代表)

|
関係性の表現の結果がコンタクトという形に 浅井: お二人が愛知の至学館大学在学中に、ダンスハウス黄金4422が主催した「ダンサーズ・ネスト」という振付家育成プログラムに参加していただいたんですよね。その頃から強靭なフィジカルとテクニックをお持ちだなという印象でした。大学卒業後に上京して、それぞれカンパニーに所属したり、いろんな振付家の作品に出演したりしながら、Nullの活動も精力的に行っていらっしゃいますが、今日はKCAで上演予定の「Own Own/オウンオウン」についてお話を聞かせいただきたいと思います。 とにかくコンタクトが特徴的で、この作品の核にもなっていますが、このコンタクトを中心にしようと思った理由は何かあるんですか? 「Own=自分自身の」という“個”としての意味があるのか、お二人のテーマである「狼狽」の「補い合う、支え合う」という概念に関係が深いのか。過去の「帰巣」という作品の冒頭にも、群舞のような、組み技のようなものが入り始めていますが、元々コンタクトが好きで、それに合うテーマ性を選んでいったのか、それとも言葉、「狼狽」や「Own」というイメージが先にあって、コンタクトの動きを中心につくっていくことになったのか、いかがですか? 岡田: 言葉が先です。 黒田: 「狼狽」が「Own Own」の原型となる作品で、当時二人で作品をつくる時に、どうしても「二人でやる意味」がほしいと思い、「狼狽=相補い合う」というコンセプトに出会いました。大学の頃につくりましたが、自然とコンタクトの動きになっていきました。 岡田: そうですね、その「狼」と「狽」というものが、支え合っていないと動けないし、補い合いながら常に行動を共にする。それをテーマに動きをつくっていったら「接する」ことの方が多い動きに、結果としてコンタクトになっていったという感じです。コンタクトの動きをたくさんつくろうと思ってつくった振り付けではなく。 浅井: そちらなんですね、面白い。お二人の動きは、日本では珍しくコンタクトにオリジナリティがあると感じています。もちろんコンタクト・インプロビゼーションだったらタスクやメソッドも数多くあるし、それぞれの個性が出やすい。しかし、ここまでしっかりとした振り付け作品にする中で、お二人を見ていると、コンタクトが振り付けやテクニックではなく、もう少ししっかりとしたメソッドとして言語化されているような印象があります。 僕は、イスラエルの振付家のシャロン・フリードマンがすごく好きで、ゆるやかなコンタクトをする方ですが、コンタクトなのに独自のアートフォーム・表現形態が確立されていて、メソッドもタスクも非常にクリアなんです。お二人のコンタクトにも、それに通じるものを感じる。どういうふうにオリジナリティみたいなものを追求しているのかな? 黒田: “体あそび”みたいな感覚でコンタクトをつくっています。オリジナリティにつながるかは分からないですが、コンタクトをやる上でこだわっているのは、「対等でありたい」という思い。作品上でも、実際の僕らの関係においてもです。僕が彼女を持ち上げる動きだけだと対等ではない。でも、現実的に僕が上になる動きは身体的に厳しいだろうと思って彼女に聞いてみると、「いや、やれるよ」って(笑)。きついけれど、とても面白いコンタクトが生まれる、そういう動きに自然とこだわっていくようになりました。 岡田: いろいろ挑戦したよね。 浅井: なるほどね。非常に面白いなと思ったのが、「狼狽」の頃は動きが“コンクール向け”、勝つための動きみたいな感じに見えていたんです。それが今回の「Own Own」では、お二人はおそらく動きの引き出しをたくさん持っているんだけど、その引き出しをあえて一旦閉めて、「とにかくテーマに対して誠実に向き合ったら、どんなコンタクトが生まれるんだろう?」と考えた結果の振り付けなのではないかという印象があるんです。似ているけれども全然違う作品になっている。その辺りはいかがですか? 黒田: 「狼狽」の時、コンクール向けにつくっていたというのは、その通りです(笑)。大学コンクールや現代舞踊のコンクール、上京後はダンスコレクションも、“競争の中の作品”という前提でつくっていたので。 岡田: 本当そうだよね(笑)。そこから少し作品が分からなくなってしまった時期もありました。まず「狼狽」をやる上で、語源でもある「支え合っていたものが急に離れてしまい慌てふためく」所から何が生まれるか、というテーマをそれほど深く考えていなかったなと徐々に気づいて来ました。そこから、この「Own Own」の前に、もう一つ「狼と狽」という作品を間に挟んでいるのですが、「狼狽」が「狼と狽」になり「Own Own」になって、次第に自分たちの関係性とより深く合致するようになってきたと思います。 浅井: そう言われるとすごく分かるなぁ。先ほど黒田さんがおっしゃったように「対等性」において、コンタクトは「力がある・ない」という筋力的な問題で、どうしてもヒエラルキーが生まれてしまうことが多いのだけど、それが振り付けなのに全く無いというのが面白いですね。 僕もコンタクトをやるので分かるのですが、二人が向かい合ったり、絡み合ったり、支え合うと、どうしてもその二人に観客の視線が誘導されてしまう。空間がギューッと身体にフォーカスしたり、身体の間にある関係性に観客の視線が誘導されたりしやすいんですよね。しかし作品となると、空間、音、光、そして身体と振り付けという、多様なマテリアルが舞台の上で共存しなければいけなくて、そういう中で20分という一定のボリュームのある作品をつくるとなると、コンタクトだけではなかなか難しいと思うんです。あれだけの長い時間コンタクトを使うのは勇気がいるだろうし、離れて踊りたくなってしまうと思うのですが、そこにこだわった理由は何かあるんですか? 黒田: 最初に二人の体が離れるまでは、二人というより「一人」で踊っている感覚が強いんです。あの状態で「一つの体として動いている」というイメージがあり、結果的にコンタクトを長い時間やっている感じです。 岡田: そうだね。 浅井: コンタクトというよりは「狼」と「狽」が合体して、一つの動物として補い合いながら存在している。だからコンタクトの動きをたくさんやっているという感覚ではなく、「狼」と「狽」の関係性で成り立っているということなんですね。
|
 「狼狽」2018年〈ART.M in TOYAMA〉 |
|
「ただ支え合う」から、「Own」と「Own」であることへの旅 浅井: コンタクトでは、もちろん「触れる」ことや、触れることで互いの心がバイブレーションする方の「振れる」も起きるし、それが補い合ったり、支え合ったり、バランスしたりと多様な事象が起こります。お二人の作品では時折、二人が触れている所にドラマが起きたり、触れている間にある関係性に対して強い意識がありそうな瞬間があったりしますが、「狼狽」を拝見した時には、僕にはそれが“テクニック”に見えました。テクニックが羅列されて、ポーズやリアクションみたいなことが起きている。 だけど今回の「Own Own」に関しては、触れている身体の間で起きている事象や感情の交換、空間や外部に対してアプローチする意識など、いろいろなものが混ざり合っていく瞬間が、コンタクト中に何度も見えたように感じています。何か「間にあるもの」とか「触れていながら外にあるもの」に対しての意識はあるんですか? 黒田: ありますね。この作品をつくっていた最初の頃は「狼」と「狽」がとても仲良しのイメージ、生きていくために支え合っているだけの関係性になっていたのですが、自分たちなりに考えを深めていく中で、「絶対、自分の時間はほしいよね」とか「絶対、自分の“欲”や“こうしたい”という思いが生まれるよね」と話していて、そこで「Own 自分自身」というものを強く置くようになりました。触れたり支えたりする動きの上でも、「自分が“こうしたい”から、支えたり、支えられていたりするんじゃない?」というイメージを強く持つようになった。 岡田: 「狼狽」の時には“幻獣”というか、“動物”という意識が非常に強かったのですが、今はもう“自分たち”という“人”と“人”の関係性でやっているので、こうした意図があることが見えるように表現しているのかもしれないです。 浅井: 「狼狽」という言葉だけがソースだったとしたら物足りなかったのですが、それをやはり「自分たちの関係性」に落とし込んで行った所がとても面白いです。それはすなわち社会にたくさんある同じような関係性の全てに落とし込める。夫婦関係であり、カップルであり、家族であり、全てはそういう関係性で社会が成立しているわけですから。お話を伺っていると、「狼狽」、「狼と狽」、「Own Own」とアップデートを繰り返しながら、作品と共にお二人が旅をしているんだなというのがよく分かります。
|
 「Own Own」2022年7月〈DANCE×Scrum!!!2022〉photo:大洞博靖 |
|
成熟した身体性が語るものと「光る玉」の質量 浅井: 僕は作品中の「光る玉」にどういう意味があるのか、ずっと気になっていて。あのボールには、どんな意味や意図があるんですか? 岡田: こう見えたらいちばんいいと思うのは、「欲」の可視化です。二人がゆっくり歩んできて寝るシーンから始まる日常空間の中で、「寝る時は電気を消す」という行為を象徴するアイテムとしてあったらいいなと思ってライトスタンドを探したのが発端。そのライトが作品上で今後も多様な形に変化していく可能性を考えた時に、この作品で重要な「欲」を表現するものとして、この丸いライトに行き着いたんです。触れると消えたり、押し潰すことができたり、反発して膨らんだり、私の中の「欲」も硬いものではなく、変形・変容するものなので、その「欲」を表現するにふさわしいと思い、この光るボールになりました。 浅井: 僕は疑問に思った所がいくつかあって、「狼狽」で使われているテープも、今回の光る玉も、二人にとっての空間性へのアプローチ、例えばプロセニアムのブラックボックスを変容させたいとか、スペースの在り方を変えたいという目的意識がすごく見えていて、コンタクトの部分がとてつもなく成熟してきているだけに、「なぜあの玉が出てきたんだろう?」というのが非常に気になってしまった。あの玉に、コンタクトの成熟度と同等の「こうでなければならない」という確固たる答えが見つかっているようには今ひとつ思えなかったので聞いてみたかったんですよね。実際、あれはこの作品をつくっていく中で、比較的新しいアイデアじゃないですか? お二人の中では、あの玉を使うということが今はもう成熟しているんですか? 黒田: そうですね、まだ突き詰め切った段階でもないというのは、正直な所です(笑)。 浅井: うん、僕はそれがすごく楽しみなんです。作品においてあの玉が「欲」だということが観客には伝わらなくてもいいと僕は思っている。でもコンタクトの完成度が極めて高いから、あの玉がこの作品において必要性や意味を持ち、最終的にちゃんと回収されていくものなんだというのを京都で見ることができたら楽しいなと思う。審査員からも話が出たんですよ、「何だろうね?」って。「でも絶対意味はあるよね」って(笑) おそらくお二人の体には、私生活や長い学生生活を通じて語らずともコミュニケーションができる身体性ができ上がっているから、モノに頼らなくても、お二人が思っている以上に語り尽くされていると僕は思います。そこでモノが出てきたから、よほど何か意味があるんだろうと逆に深読みをしてしまって(笑)。 岡田: 演出面も頑張りたいなという挑戦です(笑)。 浅井: いいと思うよ、ぜひ挑戦してください。
|
 「Own Own」2022年7月〈DANCE×Scrum!!!2022〉photo:大洞博靖 |
|
ダンサーと振付家の境界線について 浅井: お二人がなぜ「振付家」になったのかも伺いたいのですが、お二人のバックグラウンドはどんなふうにコンテンポラリーダンスへつながっていったんですか? 黒田: 僕は小学校から高校1年生の仮入部まで、ずっとサッカーをやっていました。 浅井: 踊りの中で“シザーズ”をやってましたね。 黒田: やってました(笑)。中学校の頃に友達からダンスに誘われ、見たのがブレイクダンス。それがきっかけで高校からダンス部に入りました。最初は「なんでこんなバーにつかまってるんだろう、なんでこんな手の形やってるんだろう、ブレイクダンスをしたかったのに」と思っていたのですが、神戸のダンスの大会を見た時に大学生の作品に圧倒されて「こんな人になりたい!」と思ったんです。そして大学に入ってダンスを続けていくうちに、単にブレイクダンスを踊るよりも、身体表現の一つとして、その中にブレイクダンスの動きやアクロバットが入っている方が魅力を感じて来ました。それで今、作品づくりやコンテンポラリーダンスの方へ惹かれているという流れです。今でもサッカーは大好きですし、コンテンポラリーダンスも大好きです。 浅井: 岡田さんは? 岡田: 私は3歳から高校生までずっと同じモダンバレエの教室に通っていました。高校生の時に、NHKで神戸の大会が放送されているのを見つけてから毎年楽しみに見るようになって、「みんなダンスでこんなに青春してるんだ!」と感動し、大学受験の際に、この大会に出ている大学に行きたいという動機から大学を絞り、いろいろあって最終的に受かったのが至学館大学でした。そこから部活に入り、自分たちの力で作品をつくり上げていく環境も、先輩・後輩の関係が厳しい環境も初めてで、1〜2年生のときは「部活やめたい」と思っていたんですがなんとか続けて。そこが私のコンテンポラリーダンスの起点かどうかは分かりませんが、作品創作の原点は大学の部活だと思っています。 社会人になる時に、私は就職すると決めていて、就活もしたし内定もいただいていたんです。ところが彼から「山田うんさんのカンパニーに受かった」と聞き、ダンスの道に進む彼を羨ましく思いました。そんな時、杉山絵理さんから「BATIK」というカンパニーを教えていただき、どういうものかも知らずに飛び込んでの今なので、私はコンテンポラリーダンスというものにこの2〜3年でようやく出会っているのかなと思います。 浅井: 不安はなかったですか? 僕も同じ愛知から上京してダンサーで食べていくことを決めたけれど、普通に考えると不安だと思う。僕はストリートダンサーだったから、仕事としてはバックダンサーをすればいいとか、少し見通しがあったけれど、コンテンポラリーダンスは何が仕事かよく分からないですよね?(笑)。ミュージカルでもないし。不安とかなかったですか? 岡田: 不安はありましたし、今も不安(笑)。でも、それこそこんなふうにお互いにカンパニーに入るという決断がなかったら、東京にも来ていなかったかもしれない。その分岐点は大きいなと感じます。 黒田: 僕は絶対に就活したくないと思っていました(笑)。就職したら、絶対にダンスをやめてしまうだろうなって。働きながらダンスを続けている人もいますが、僕はきっと仕事でいっぱいいっぱいになってしまって、結局ダンスの方が無くなってしまうだろうと思ったので。運良く今のカンパニーに入ることができ、上京して今に至るという感じです。 浅井: そこからお二人はそれぞれカンパニーに所属しつつも、わりと早い段階から創作に入っていったと思いますが、兼業というか、振付家になろうと思ったきっかけはあるんですか? 振付家を志したというより、元々のユニットで作品をつくっているという感覚なのかな? 岡田: 「振付家になろう!」と思ったというよりも、大学の部活の延長線上という感覚が私は強いです。でも何か、ダンサーだけに留まりたくはなくて、やはり創作することも好きだからここまで続いていると思いますし、さまざまな振付家の作品に出てつくり方を見ていても面白い。「じゃあ、自分たちだったらどうできるんだろう?」という実験の場がNullとしてある。それが最も良い位置だから活動が続いているんじゃないかと思います。 浅井: ダンサーの活動がメインで、その延長線上で自分でも振りをつくってみたいという場合は、所属しているカンパニーの動きをトレースしたりしがちなんだけど、お二人はそれがあまりないように見えます。特徴も全然違うカンパニーにいるし、「Own Own」に関しては、作品を作るのではなく「自分たちのオリジナリティをつくる」メソッドとか、「メソッドがある作品をつくる」姿勢に向かっている気がします。それは「ダンサーとして踊っているから、自分でもつくってみたい」という感覚とはかなり違う。僕からするとお二人はとても正統派のダンサーで、みんなと同年代のダンサーたちとは少し違っているように感じます。同年代のみんなは、もっと等身大に、自分のバックグラウンドやライフスタイル、嗜好性みたいなものと向き合いながら、バレエやストリートダンスのテクニックもジャンルレスにミックスして創作していくスタイルの子が多いと思うのだけど、お二人はもう一つ上の世代の人たちと同じような創作の仕方をしている印象があります。だから「振付家になりたい」という意志が明確にあったのかなと作品を見た時に思ったんです。 岡田: 意識してた? 黒田: ダンサーと振付家というものにあまり境界線がなく、一緒であったらいいのにという気がします。表現者として。 浅井: なるほどね。実際はどうですか? 一緒だと思っている? それともやはり違う? 黒田: 僕はたぶん一緒です、踊ることと、つくることは、僕の活動としては一緒。だから僕が「振付家」、「ダンサー」と呼ばれるのではなく「表現者」みたいな存在だったらいいなと思います。会話の中でも「お前はダンサーじゃん」みたいに言われたりすると違和感があって。「ダンサーはつくっちゃいけないのか?」と。 浅井: 僕もソロの作品でコンペにたくさん出ていて、自分の体を自分がいちばん知っているので、ダンサーと振付家の境界線がなかったんです。デュオも同じで、プライベートも踊りのことも全部分かっているパートナーと作品をつくってきたから、ダンサーと振付家の境界線がない。でも、これが例えばカンパニーがあって、そこに属する人たちの自分とは全く違う身体性に自分のメソッドを移植することになった時に、「振付家」として初めて考えなきゃいけない段階になるんだと思う。お二人はカンパニーでも働いているから、ダンサーとしてのその感覚はよく分かっていると思いますが、自分たちの作品をもし誰かに振り付けすることになった時には難しそうだなって思ったりします? 黒田: 難しそうとは思いますが、とても興味はあるよね。 岡田: うん、興味はある。それこそ2人でも3人でもそうですが、議論しながらつくるので非常に時間がかかるんです。だから分かり合えるメンバーが見つかるといいなとはずっと思っていました。つくる上で誰が主体か区別しなくていいとも思うし、他の振付家や出演者がいる中で一緒につくることにも挑戦してみたいですが、怖いと思う自分もいます。身内だからこそできている今この時間、この作品だとも思う。でも、広げていきたい思いはありますね。 浅井: 先ほど正統派と言ったのは、そういうことにも関係していて、お二人の作品を見ていると、一歩引いた状態で自分たちの作品を見ることができているバランス感覚があると感じるんです。作品の中に没入してしまって、自分が作品のパーツの一部になるというよりは、作品は作品として自立して生きている。もちろんそこで踊っているのも、つくっているのもお二人なんだけど、でも作品をちゃんと自分たちから外側に出している。 それができるということは、すなわち、「どんなふうに作品がつくられているか」とか「この動きにはどんな意味があり、どうコントロールされているのか」を言語化できているんじゃないかと。そのくらい精密に作品がつくられている印象があります。 そういう人は基本的に振付家になっても言語化できる。自分だからできるんじゃなくて、人に伝えられる準備ができている印象があるんですよね。それで今はお二人ないしは三人でやっているけれど、いずれは振付家として自分たちのスタイルを人に伝えたりしたいのかなと。それが作品を見た時の印象になっているんです。
|
 ブレイクダンス時代の黒田  モダンバレエ時代の岡田 |
|
あるはずのものを捨て去るところから始める 浅井: 「帰巣」はじめ他の作品は、Nullが持っているテクニック、例えば大学ダンスの群舞やモダンダンス的な要素、アクロバットなど、わりと引き出しの中身を全部詰め込んでいる印象でしたが、今回の「Own Own」になった途端に、引き出しを勇気を持って閉じて、「狼狽」というコンセプトに向き合うという強い姿勢が見えています。これは何か、自分たちの創作テーマ、「ゼロから考える」ということに関係しているんですか? 「Null」は「ゼロから」という意味があるんですよね? 岡田: 一旦物事をゼロから、自分たちならどう考えるのか。「こうあるはずのもの」という概念を一度捨てることから「Null」は始まっています。私たちは「狼狽」というものに固執していましたが、その自分たちを、「狼」と「狽」も一体と一体の関係性であるという概念に持って行けたことが、今回の「Own Own」につながっていると思います。 黒田: 「Null」には「ゼロに戻す」という意味がありますが、元々、僕と岡村(もう一人のメンバー)で踊ろうとなった時の作品のタイトルが「Null」でした。 それを、ダンスグループをつくる時に、グループ名にしました。その時は「ゼロ」とか「常に原点を思い出して」という意味を持たせていたのですが、「Null」をやっていくにつれて、「Nullと言えば何だろう?」という問いが生まれました。結局その答えはまだないですが、そういうものはほしい。じゃあ、何にこだわってつくるかを考えた時、せっかく「Null」という言葉があるのなら、物事をゼロから考えるスタイルや考え方でつくっていこうと。 浅井: なるほど。今はまだ自分たちでは「Nullと言えば○○」というスタイルが見えていないとおっしゃっていたけど、外側から見ていると、作品にはすでにスタイルはあるなと思いますよ。自分たちから見るものと、外側から見るものとでは全く違うから核心かどうかは分からないけれど。今後はどんなふうに活動や自分たちの創作スタイルを発展させていきたいと考えていますか? 「チャレンジしたいこと」とか「こんなことやりたい」ということでいいのですが、言っておけば、誰かが記事を読んだ時に叶えてくれるかもしれないよ(笑)。 岡田: チャレンジか。チャレンジとしては40〜60分の作品をつくりたいと思っています。それから、この身体性はずっと持続させていきたいね。 黒田: ダンスでいろんな所へ行きたいな! 岡田: 海外へ行きたい。 浅井: 海外はNullでは行っているの? 岡田: 行ってないです。 浅井: でもきっとお二人の作品は、いろんな所を旅できると思います。それは作品の強度もだし、旅がしやすいというか、パッケージもスーツケースで可能だと思うし、いろんな国の人たちに普遍的に伝わるテーマだと思うし。こういうKCAみたいな機会をいろいろと活用して、コンペやフェスに積極的に出ていけば、きっとどこへでも行けるようになる。ぜひチャレンジしてほしいと思います。 岡田・黒田: はい、チャレンジし続けます! (2022/11/14 zoomにて)
|
 稽古の様子
|
|
振付家 岡田玲奈(オカダ レイナ)、黒田勇 (クロダ ユウ) 作品概要「Own Own」 〈狼狽〉という言葉の語源には互いに欠点があり、それを支え合いながら常に行動を共にする狼(ろう)と狽(ばい)の関係が存在しているそうだ。一見、この関係性には思いやりがある温かい印象を抱く。それは「支え合う」という言葉がそうさせているのだろう。互いが互いを支えるというのが「支え合う」だが、二体も自らに欠点があるから相手を支えて成り立つ関係であって、ただ相手の為に支えているわけではない。「支え合う」という行為には見えていないだけで、無意識のうちに自分自身の欲が存在している。このような考えに至ったが、あくまで「支え合う」関係性には変わりない。 インタビュアー 浅井信好
|
|
「KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2022ー若手振付家によるダンス公演&作品を巡るディスカッションー」 Interview |