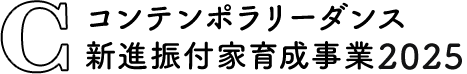Report/Survey
レポート/アンケート
大月侑
振付家・ダンサー
参加プログラム
<2024年度>
山代温泉『空間感覚で広がる振付・演出の世界2024』
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、特に今後の活動のプラスになったことなど。
小屋入りから本番までの期間に、一般の方を含め多くの方に作品へのフィードバックをいただけたのは非常に良かったです。上演後の自分の感覚と、皆さんからいただいた意見とをすり合わせていくうちに、”ダンスとはこうあるべきだろう”という考えにとらわれていたことに気づきました。作品の要素を根本から見直し、
・作品のコンセプトに直接関係する言葉を使うこと
・既存の音楽を排除すること
など自分にとって新しい手法に挑戦するきっかけになりました。またその過程を通して、私はダンスをやりたいのではなく、人間の身体の面白さを追求して、それを人に共有したいのだと、考えを確かめることができました。今後の活動の選択肢がグッと広がったような感覚があります。
またとらわれていたことという観点では、もう一点、空間の使い方があります。専光寺という広がりのある空間で、お客さんにもその広がりを味わってもらうために、空間を大きく使わなければとがんじがらめになっていた自分がいました。しかし、今回の作品の中身をきちんと届けるには、アクティングエリアを狭くした方が良さそうだという考えに行きつき、最終公演では本堂の半分ほどの大きさで完結する作品に変わりました。最終公演をご覧になったあるお客様からは、”皮膚”という近くのことをやりながらも、すごく遠くのことまで表しているように感じた、というご感想をいただき、空間を大きく使うことと、自分が作品の中で取り上げている世界の大きさを表すことは、必ずしもイコールではないのだなと感じました。今後も、さまざまな空間で上演を続けたい作品ですが、空間の使い方について新しい見方を得られたのは大きな収穫でした。
<2023年度>
山代温泉『空間感覚で広がる演出・振付の世界 vision+』
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、特に今後の活動のプラスになったことなど。
お寺での公演を初めて経験し、普段立っている”劇場”が、いかに守られた空間であるかを再認識しました。アクティングエリアと客席の位置を考えることから始まり、毎日変わる天候の影響も考慮しながら、空間について学ぶ非常に良い機会になりました。場合によっては、稽古場で作り上げたものを捨ててでも、作品を上演する空間をしっかり捉えて、いかに空間をよく見せるかを考えなくてはいけないということを身をもって学びました。”地方の”・”お寺で” ダンス公演をするということで、単に自分の作品の在り方だけでなく、公演の組み立て方やお客さんへのアプローチについても今一度考えるきっかけになり、得るものが非常に多かったです。企画者の山田さんをはじめ、講師・スタッフの皆さんから濃密なフィードバックを受けることができ、振付家としての思考を見つめ直す機会にもなりました。
また、今回は石川県で採集した竹や流木を使用し、それに対するフィードバックもお聞きしながら、小道具と空間の関係性を探れたことはもちろん、小道具の意味合いや、ものの振動を身体がきちんと受け取っているかなど、作品を詰めていく段階で検討すべきところを洗い出すことができました。今後の創作でも、単純に筋が通っているかだけでなく、空間・身体などあらゆる方向からものと向き合うことを大切にしたいと思います。