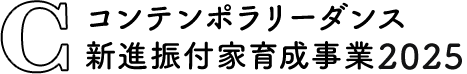|
馨子
(長野県
安曇野市)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
事前に「振付」ということを考えたときに、「振付」をするということは、表現したいことを深く考えることにつながるということに気付いた。
そして作ることは反芻し、試し、崩し、創っていくこと。
同じことを違う面からとらえたり、表現したり、自分の中でまた知ることが出来ることだと思った。
普段は即興でパフォーマンスすることが多いが、この反芻して考えることは即興でも生きることだと思った。
また、振付をする、踊るということは、その動き一つ一つに「こだわり」を持つことだと思った。なぜ、今この指なのか腕なのか、力なのか、感情なのか、質感なのか。
なんとなくではなく、これである必然性を考えることもまた一つ深まることだと感じた。
|
|
稲井咲紀
(長野県
佐久市)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
長野に移住してきて4年目で、自由に踊るコンテンポラリーダンスに出会って3年目。この3年の間に、自分自身への振り付けを考えて踊る機会が2回ありました。そこでは、自分が考えていることを言葉ではなく身体で表現することのおもしろさを感じつつも、その成果への手ごたえは薄くて、どこへ向かっていきたいのかに彷徨っていました。
今回の振付キャンプでは、3人の振付家の方と出会い、15人もの振付と踊りに執念を燃やす仲間たちと時間を共に過ごすことができました。たくさんの方のダンスを見て、創作に至る過程にふれて、メンターの方の言葉に内省が起こりました。鈴木ユキオさんに「自分がどうしたいのか」を投げかけられた時、どうしたいんだろうと立ち止まり、今までの振り付けでは伝えたいことがはっきりとしているあまり、仕草の動きが多かったのを、ダンスにしたいと思いました。二瓶野枝さんが身体で遊ぶことで振付をつくっていくことをお聞きし、夜遅くまでその動きに挑戦することができました。実際、本番で踊ったものをみると、自分が想像していたものよりゆっくりで仕草になっていることも多くて、まだまだの出来でしたが、自分にどんな癖があって、どうなっていきたいのかに気づくことができたことがとても嬉しいです。私の考えとダンスに寄り添ってくださったメンターの方のおかげです。また、メンターと他の参加者からのアドバイスに、自分を客観的に見ること、踊りの中に緩急をつけることがありました。客観的に見ると自分の踊りがどう見えるのか、それを私はどう思うのかという視点は、ダンスの世界だけではない話だと思います。私は今、教員として5年目で、毎日忙しいながらも、充実した時間を過ごしています。自分の振る舞いがどう子どもたちに伝わるのか、それを私はどう思うのか、そして私はどんな教員を目指していきたいのか。そんなメッセージのようにも受け取りました。日常的にできるだけダンスにふれ、踊りたいと思っています。それは、教員としての自分の幅を広げたり、自分を違う視点から見て理解を深めたりできる気がするからです。今回はキャンプという濃密な時間で、ダンスと自分と向き合うことができました。本当にありがとうございました。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
今回の取り組みで、サポートしてくださった、香さんと美里さんに感謝申し上げます。いつもありがとうございます。また、個人の思いと努力によって、長野県のダンス文化が賑わっていることも痛感しました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
|
|
小松順子
(長野県
上田市)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
経験の有無、年齢にかかわらず、幅広く参加者を受け入れてくださったことが良かったと感じます。そのおかげで普段は交わることがない世代の人と同じ時間を共有できて、とても刺激を受けました。
今回は自分なりの創作の仕方を見つけたいと思って参加しました。メンターの方の創作の方法を聞いたり、他の方の創作の進め方をみることで、自分と違う視点の創作の仕方を知ることができました。これからの創作のヒントにしたいです。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
創作の時間がもう少しあるとよかったと思います。
座学(クロストーク)もあって盛りだくさんで楽しかったのですが、創作の時間がもう少し欲しかったです
|
|
司白身
(長野県
小諸市)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
メンターの言葉で、ずっと引っかかっていたことへの糸口がつかめました。応募動機や、振付のテーマや目的を丁寧にヒアリングしていただけたことで、カラダに向き合いやすくなりました。
もともと演劇をしていたのですが、心地悪さを感じて長らく離れていました。しかし周りには演劇人も多いので、カラダと向き合いながら、どこかで「ダンス」「演劇」の併存について探っていました。こんかい振付と向き合うことで、ずっと引っかかっているダンスと演劇のレイヤーについて、手がかりをつかむことができました。
またカラダが持つ癖やノイズを意識すると、ぎごちなく、わざとらしくなってしまうなど、これまで消化できずにいた必要なことへの向き合い方が、カラダで理解できた瞬間もありました。
カラダで閃いて脱線していく、やり込むことで抽象的になっていく。カラダへの探求が振付につながるのだと感じました。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
タイトなスケジュールだったので、やりたいことを絞って挑みました。3時間に及ぶトークセッションは、振付家とともに舞台を創る専門家のトークなど、振付に特化したセッションだとよかった。
|
|
本澤夕湖
(長野県
塩尻市)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
4日間、同じ方向を向いて、もがいてもがいて必死に踊りや振付とは何かということに集中出来る時間や機会というのはなかなかないのでとても貴重でした。全く畑違いの人達の振付や踊りの考え方や作り方をお互いに話し合い、そして常に伴走をしてくださるメンターの方からアドバイスを頂き、自分の振付や踊りに対する考え方もこの4日間で大きく変わりました。最終発表を終えてから気付いたことも沢山あり、振付キャンプが終わっても、このキャンプで気付いたことや考えたことがまだまだ続いています。キャンプという形で色々な人達と振付に向き合うことが出来て良かったです。
|
|
原山聡矢
(長野県
松本市)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
「山あいの振付キャンプ」(以下、本キャンプ)の上位事業が「新進振付家育成」を謳っていることと自分の属性を考え合わせた時、正直申込みを臆する気持ちがありました。自分は初心者ですが「新進」というには歳を取りすぎているし、普段アカペラ歌唱を軸にしていて、そこにダンスを組み入れようという目論みだからです。しかし、本キャンプを知るまでの流れは何か導かれるようであり、「迷わず行けよ、行けばわかるさ」の猪木イズムで、参加に踏み切りました。
コンテンポラリーダンスには「動きがうにゅうにゅしている踊り」という幼稚園児レベルの感想しか持っていませんでしたが、本キャンプを経過して、そのような外形的なことよりも「個」から発するダンスなんだ、という認識を持ちました。
発表時間10分を与えられ、前半は会場の環境を利用した表現、後半は既存の楽曲を使ったのですが、メンターから丸々一曲(4分間)振付たことについてのご指摘がありました。特殊なことだったようで、だとすれば、むしろ今後意識的に取組んでみる価値があるのかも知れません。ダンスに対する取組み方や表現プラン、「振付とは何か」について等、言葉にする時間が長く持たれました。相当ドラスティックな意見も出ましたが、メンターの皆さんが口を挟むことなく傾聴する姿勢に感銘を受けました。講師でなくメンターと呼ぶ意味が分かった気がしました。各メンバーが、ただ作品を作るだけでなく「どう見て貰うのか」まで見据えていたのが印象的です。もとより全員で一つの作品を作るのではなく、各個人がそれぞれの表現を追求する場にも関わらず、チームの一体感を感じられたことは軽い驚きであり、得難い経験でした。
今後は、今回の発表をもとに一つ作品を仕上げてみるつもりです。最後になりましたが(例えば、上履き持参の提案メールなど)ADN nagano の皆さんのきめ細かい運営に感謝申し上げます。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
前項では全体的な感想を書きましたので、本項では(趣旨にそぐわないかも知れませんが)自分の備忘も兼ねて、最終日のショーイングに至る経過を書いてみます。まず、キャンプ前の準備ですが、自分はダンス鑑賞の蓄積もなく、振付を考える手がかりすら乏しい状態でした。これまでに見聞きしたものをかき集めて考える他手立てがありません。血圧の薬を日数分ジップロックに詰め替えながら、既存の楽曲を2曲選びました。
(将来的にはオリジナルでやりたい気持ちがあります)
Jazz Police(Reonard Cohen, Jeff Fisher)https://www.youtube.com/watch?v=j7YebrCuqsU
Oh Yeah(CAN)https://www.youtube.com/watch?v=qKpCKBfazX8
コンテンポラリーダンスで用いられる音楽はミニマルなものが多い印象ですが、前者はボーカルが全面的に入っており、後者は反復ビートが特徴ながら基本的にバンドサウンドです。どちらもダンスを想定した曲ではありません。単純に好きな曲を選んだ感じです。
後者は長尺(7分22分)なのと、前者のコーエンは長く聴き続けているアーティストということもあり Jazz Police を選びました。彼には珍しいビートの立った異色作というのも面白いと思いました。それ以外はノープランで臨みました。
何かのメソッドに基づいたワークショップではなく、各人の主体性による制作をサポートするキャンプだろうとは予想していましたが、振付を考えるのは非常に困難でした。
歌詞の説明ではジェスチャーゲームになってしまうので、歌の主題は踏まえつつヴァースごとに動きをザクッと考えてみました。途中から「厳密に振り付けたとしても覚えられないし、思い出しながら動いていたのでは勢いが出ないな」と諦めて、最後の方は即興で動くことにしました。後で動画を見ると、ヴァースの最初の方は約束事を思い出そうとしていて、苦笑してしまいますが。
もう一つの問題は、ショーイングが10分と指定されたことでした。Jazz Policeは4分の曲なので残り6分を何とかしなくてはいけません。体育館の小部屋のような謎スペースにいて、他の皆さんのしなやかな動きに見惚れたり、そこにある運動用具を触ったりしている内に、日頃参加しているインプロヴィゼーションのセッションを思い出しました。その中に「打楽器の時間」があって、全員打楽器でセッションするものです。自分は自宅から鍋とお玉を持って行ったり、その場にある段ボールを叩いたりすることもあります。そこで、体育館を楽器にすることを考えました。あちこち叩いたり揺すったりしてみて、その動線の中で動きを入れていくことや、仰臥してドーム型の天井に声を響かせる(ここは休憩も兼ねる)などで構成を試みました。発表の空間を利用することで(合宿という日常でない場なので尚更)一回性が生まれる、言い方を変えると作品発表ではなくライブにしようと割り切って考えました。
中間発表の後に「発表には原則タイトルを付けなさい」となって「聞いてないよぉ」と思いましたが、
I can’t forget but I don’t remember what.(忘れられないのに、それが何か思い出せない)https://www.youtube.com/watch?v=o-58u8Lyvhwとしました。
アルバム中Jazz Police の次に入っている曲の一節です。タイトルが最後に出る映画や、ビートルズのHelter Skelter https://www.youtube.com/watch?v=Uk1hCSA89fcで最後リンゴが叫ぶ I’ve got blisters on my fingers! (指にマメが出来ちまったよ!)をイメージして、最後に言うことにしました。噛んじゃいましたけど。
結局、振付は相当ラフなものになりました。自分は、身体能力と技術が欠如しているので、そこをショーマンシップと発汗量で補う他なく、最後の方はメチャクチャでも良いのでとにかく動くことを考えました。「これは、老人がヤケクソ気味に暴れているだけですね」と言われても否定はしません。最終発表は、荒削りもいいところですが、何とかやり切った感じです。皆さんのリテラシーの高さに救われたかも知れません。
自分は、概念的なことがよく分からないのでフラットな内容になってしまいましたが、制作を振り返ってみました。
もちろん、メンターの皆さんや他の参加者の方々からも大いに刺激を受けました。ただ、ここで書くのは僭越な感じもするので、今後、直接感謝をお伝えしていきたいと思います。
ここまでお読みくださり、有難うございました。
|
|
髙橋春香
(東京)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
山あいの振付家キャンプでの気づきは2つあります。
①観客に「見せる」ということを意識した創作。
昨年度から創作方針を変え、コンセプトを重視した創作を行ってきました。常に動機や意味を作品の重点に置いています。しかし、視覚的な面白さと両立できなかったり、観客への鑑賞体験に配慮できなかったり、結果としてコンセプトが伝わらないという状況になりがちということにこの合宿で気づきました。自身はプロジェクターを使ってテキストを身体に投影するパフォーマンスを発表したが、日中であることや文字の大きさなどの関係で、テキストが見えにくくなってしまいました。テキストが読めないために、意味が伝わらず、「よくわからない作品」になりました。
②ダンスというものの尊さに気づきました。他の参加者の発表や創作過程を見て、身体表現でしかアクセスできない情報があるんだなと思いました。それは、自分の記憶だったり、言葉にできない感覚だったり、だれかと繋がるということ。
この合宿でメンターの方々や他の参加者と協働できたことが貴重な経験になりました。自分とは全く違うバックグラウンドを持つ人たちからの意見を毎日浴びられるような環境で、毎日視野が広がっていくようでした。合宿という形だからこそ人と人の距離が近く、ちょっとした悩みを打ち明けられたり、くだらない話ができたこともすごくよかったです。
|
|
日比野桃子
(秋田)
|
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
集まった人たちの多様さが面白く、そこに「振付とは」「ダンスとは」といった命題の一つの答えが詰まっているかのようでした。それぞれがそれぞれの踊りをそれぞれの言葉で伝えようとする時間が、とても豊かなものだったなと思います。それに応えようとするメンターの言葉にも力があって、励まされました。
私は今回の参加動機として「振付というものがよく分からない」と書きましたが、そこにはきっと、「踊りを作品として提示する」ことの意味を、根本から、もういちど疑いをもって確かめたい、という気持ちがあったのだと思います。正直なところ、この疑いはキャンプを経て深まった(というか、思い出した)のですが、それは私にとって、とても大切なことでした。
と同時に、「振付」を考え踊りの準備をし発表する機会を持てたことで、発見も多くありました。振付の手法は踊る人の数だけあって、その言葉が示すものは「所作の決定・指示」であったり、「所作を促すルール」であったり、「体の造形」であったりと幅広く、踊る人や状況によって全く異なるということ。そして、それぞれがそれぞれの「振付」の形を探し、それを追求することで現れる踊りがある、ということを身をもって体感できました。
合間に開催されたトークイベントも有意義な時間でした(分藤大翼さんが見せてくださったバカの踊りは、私がキャンプ中に出会った「踊り」「振付」の中でも最も共鳴できるものでした)。
私は「踊る人がそれをどう楽しんでいるか」をみるのが好きです。その振りがどう付けられるか、何を描くかということよりも、その振りをどう踊るか、どう楽しむかに関心があります。これまでなんとなく食わず嫌いしていた「振付」ですが、食べてみることで出てくるおいしい実に触れられたことが、大きな収穫でした。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
参加者の興味、課題意識の幅広さは本当に面白かったのですが、「振付」そのものを思考することにプログラムの焦点を絞るとすると、たとえば、あえて上演のテーマを統一のものにする(難しいものではなく、たとえば「石」とか「木」とか、人によって重くも軽くも思考できるような言葉)など、それぞれの「創り方」の違いがよりはっきり見える工夫もできるのかな、と思いました。
|
浅沼圭
(東京) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
今回のプログラムでは、自分がこれまで関わってこなかった異なる分野の方々と作品作りをする機会を得ました。それぞれのバックグラウンドや価値観、考え方がどれほど異なるかを改めて実感し、さらに作品に対する情熱的な姿勢に驚かされ、その熱量に触発される日々でした。彼らと一緒に活動する中で、自分が「身体で表現すること」に特化していること、そしてその方向で作品を作ってみたいという気持ちに気づきました。また、これまでの主な活動ダンサーとしての楽しみ方、(与えられたタスクに基づいて身体を使ったアイデアを出すなど)自然に行っていた自分の「当たり前」にも気づかされ、大変貴重な機会になりました。
これまでの仕事では与えられたテーマに沿って振付を行うことがほとんどで、自分が本当に作りたいものに向き合う機会はほとんどありませんでした。今回、そのような新たなチャレンジに取り組む機会を得て、最初は正直なところ怖さも感じましたが、自分の中にこういった考えがあるのかと新鮮な気づきを得ることができました。
演出や魅せ方については、これまであまり深く関わってこなかった分野でしたが、今回の経験を通じて、どの要素を強調し、どの部分を省略するかという取捨選択を行うことで作品が浮かび上がることに気づきました。振付家としての新しい挑戦に向き合う中で、メンターの方々の体験談や振付の醍醐味に触れ、とても充実した時間を過ごすことができました。
これまでダンサーとしての活動を中心に行ってきたため、振付家や作品作りの立場に対しては距離を感じていました。しかし今回の経験を通じて、その視点に触れることができたことで、今後はダンサーとしての活動を続けながら、自分の作品作りにも挑戦し、表現の幅をさらに広げていきたいという強いモチベーションを得ました。この度は本当にありがとうございました。
|
菊池希実
(京都) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
今回、改めて自分が人に対して、少なからずの苦手意識を強く持っているのだなと確信しました。
まず一に「表現することに抵抗がある」ということを学びました。これは、芸術を含め全てにおける表現が、私に軽いダメージをほそぼそと与えることから発見されたものです。私は認識されることを嫌います。よって、己の感覚器官や物理的な遮蔽物、または私を見てしまう恐れのある観客というものの感覚器官を閉ざすことを課してみました。実際にそれらを課すと、私は表現することを行うことができるという結果になりました。つまりそれは、私の中に表現自体についての抵抗感や、表現することで受けるダメージを軽減したいという欲があるということではないか、という結論に行き着きました。
次に、「枠があることの再認識と枠がないことを好む自分がいること」を知りました。例えば時間や空間、人間の性質などにはある一定のラインがあり、それを超えると変化が起こると私は考えています。私は、そのラインを超えずにいることが苦手かつ居心地が悪いと思っていました。作品の時間はなんとなく長過ぎたり短過ぎたりがいいし、観客というものとの距離はなるべく離したり同じ高さに置かないようにしたいし、ひとつの繋がった空間ではなく空間という枠組み自体がないことを好み、そこから生まれる人間の変化や、完成といった枠組みという名のラインのその一歩先に興味があるということを知りました。
最後に。私には、「見られたくないのに見てみてほしい(こっそりひっそり覗く程度で)」という矛盾や、なぜ性質と合わない「表現」を行うのかといった謎があります。その答えはまだ見つけていません。見つけるつもりもないのですが、なんとなく良いなという感覚的なものでそこに居ます。いつかピコンと答えのそばにいるのかもしれませんが、このキャンプで得た情報と体験を整理して、まあ生きてようかなと思いました。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
思ったより細かいスケジュールで、みっちり詰まっているなという第一印象でしたが、終わればあっという間でした。それぞれで活動する時間、みんなで活動する時間、ちょっとずつ長かったり短かったりと、その時間の充実感から終了後に得る印象は変わりました。
私の行動不足ですが、どのように作品というものを組み立てるのか、そのきっかけをどのように発見したのかという始まりの前や、なぜそれを表現しようとしたのか、ダンス以外だとどのような表現方法ができるのかとった終わりの先などが気になったのかもしれないと後日考えつきました。
総じて、思考の巡りが久しぶりに良いと感じることができました。ありがとうございます。
|
望月寛斗
(神奈川) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
本企画では、今まで細かく精査できていなかった自身の振付のディティールや感覚の言語化が出来た(進捗があった)とともに、今まで踏み込めなかった実験的なことや悩んでいる事を思い切ってトライしてみる。ということができたのはとても収穫でした。
また、冠着荘という空間や合宿という特殊な制限の中での制作/振付を考えるという事は、今後のレジデンス制作などにも役立つ可能性があり、かなり良き時間を過ごさせていただきました。他にも、他の参加者との交流やその事で発見があったり、中間発表の緊張感と最終日のショーイング後、全員からのフィードバックしていただいた事はどれも刺激的です。
ショーイングについては、作品発表!という場ではなかったことは個人的に有難く、時間的なゆとりはなくても、気持ち的/精神的にゆとりを持って取り組めた(悩むことができた)のは大きいです。
〈振付を丁寧に考える〉〈悩んでいる事についてアウトプットする場があり、すぐにレスポンスしていただける〉〈ショーイング後すぐに感想を貰える〉という、自主公演や東京での作品制作の際に、丁寧に取り組みたい!と大きく願いつつも様々な事情で取り組めていなかった要素が網羅されていて、個人的にすごく良い経験値となりました。
そして、参加者のアイデアや行動力を取りこぼさないように、寛大な心で準備してくださり話を聞いてくださった、jcdnの方々ADMnaganoの方々メンターの皆さまには本当に感謝しております。ありがとうございました。
|
堀 早央里
(東京) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
振付とは?という問いかけから始まった合宿でした。その答えとして、あってるあってないの話ではなく自分の中でしっくりくる答えには辿り着きたいと思いながら考えていました。
じぶんの中でしっくりくる。
これは、3泊4日考え続けていたことだったかもしれないと振り返ります。頑固さと柔軟性のバランスがオリジナルになると思いました。
つくるということは、無限のような選択肢から何を選ぶか…という脳味噌が煮えてしまいそうな作業だと言うことを思い出しました。
孤独で窮屈で、それは自縄自縛なんだけどそこから打破できず、中々前に進めずにいる。私にとっては、それが中間発表を終えた夜です。
メンターのお二人に強力なアドバイスをいただけたのにも関わらず、力量不足で手詰まり状態でした。
閃きは、かけた時間で起こるものではなくて日々の準備や経験から起こるものだなと実感しました。
何度かあった話し合いや、最後の発表では、今まで来た道がそれぞれあってそれが考え方や振付(作品)に反映されているなとすごく感じました。だからやっぱり日々をいかに過ごすか、生きるかだなと思いました。
今後に活かしていきたいと思います!
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
プログラムの趣旨を見て、参加したいと直感しました。
メンターのお三方、参加者の皆様、JCDN、ADM長野の方々、関係者の皆様のおかげでとても豊かなひとときを過ごさせていただきました。今回でのこと、時間はかかりそうですが、自分の中で再考していきたいと思います。
貴重な機会をいただいたこと、心からありがとうございました!
|
富永あみ
(神奈川) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
4日間、ありがとうございました。普段、創作する段階や、他の方の作り方を知る機会もなければ、そのテーマで話すこともないので、とても大きな機会でした。メンターの方のアップや創ってきた過程、大切にしてること、振付家ではない芸術家の方からのお話、本当に沢山のことを聞いて、見て、触れて、感じることができ、自分の活動のプラスになるものばかりでした。振付ということに向き合いながら、”創る自分”にずっと問いかけられる時間もこの自然の中だったからできたんだろうなと思います。そして、ショーイングでは、色んな視点、価値観、考えをもった皆さんから意見をいただけて、とても貴重な機会でした。
これから、考え続けて、作り続けた先にあるものをやっぱりみていたいし、ダンスって何か、振り付けって何かをまだまだ考えるきっかけになりました。本当にありがとうございました。
|
國松寛太郎
(東京) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
以前自分で振り付けの創作をしたときは、本当に何をしたらよいのか分からないまま暗闇の中を一人で歩いているような感覚で模索してやっていたので、出来上がった作品にもあまり自身がありませんでした。そのため、他の人がどのような過程を経て創作しているかということについて知ることができる合宿に参加できる機会を得るのは非常に楽しみでした。今回のプログラムでは、3人のメンターと何人かの参加者と寝食を共にして創作活動するという貴重な経験させていただきました。参加してみた結果、他の参加者が創作しているのを見て、そんなに簡単にうまくいっているわけではなく、皆も自分と同じように苦しみながらやっているのだということがよくわかりました。やり方も人それぞれで、出来上がった作品も全く違うものでした。参加者からの意見では、自分がそこまでよくないと思っていても他人からすると魅力的に映ったところがあったのが意外でした。他人の目を通じて自分を知る非常に有意義な時間でした。また、メンターの方々等からの鋭い言葉は、脳裏に鮮明に焼き付いています。ダンスだけでなく、自分がどう生きるかに結びついている気がして、目を背けたくなる気持ちや後悔の念等も感じることもありましたが、創作や振り付けの本質を考える良いきっかけとなりました。集中すること、深く掘り下げること、観察すること、これらは自分に足りていないところで、今後の自分の課題ですが、その出発点となるのは、「動機付け」だと思うのです。自分自身動機はそれほど持っていないと思っていましたが、本当はあるのだけれど気づいていないのではないかと考えるようになりました。何か創作の機会があれば、最初から完璧なものを目指さず、「とりあえずやってみる」を繰り返しやっていくことで経験を積み重ねていけば、何か発見できるようになってくるのではないかと感じます。
プログラムに対してのご意見・ご感想など。
パンフレットの写真は、芝生の上で気持ちよさそうに活動している写真があったので、それを期待していましたが、実際には基本的に室内でしかできなかったのが少し残念でした。
|
長田萌夏
(神奈川) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
4日連続で朝から晩まで振付に集中する機会は普段の断続的な生活では中々取れないので大変貴重な経験だった。
人の声や車の音よりも虫の声が多く、いつもとは違う環境に呼応する身体も変わり、自己をスタジオに隔離して作る創作では出ない動きが生まれた。振り付けの幅もブラックボックス以外を使った創作も視野に入り、舞台に用いることのできないプロップを使った作品も創作できた。
バックグラウンドも経歴も異なる方々が参加される中で物事への価値観の違いだったり、自分一人では発見出来なかった癖や見方を教えてもらった。その中で発見した別の創作方法にチャレンジすることが出来て改めて自分の現状のボーダーラインを認識できた。ショーイングの前に設けられた中間発表があったことによってメンターの方だけでなく他の参加者の方に相談したりして作品を発展させることができた。このワークショップで認識した発見更に深く広げていけるように今後の創作活動に生かしたい。
|
安永ひより
(千葉) |
参加されたプログラムについて。発見したこと、吸収できたこと、振付家(または振付家を志している)の方は、
特に今後の活動のプラスになったことなど。
わたしにとって何が創作のモチベーションになるのかについて向き合えたことが、今回の大きな収穫です。振付とは何かについて対話し、思考し続ける4日間でした。それぞれの考えからヒントを得ながらも、私はどう考えているのか、その解を作品へ出力し続けることで答えていくような期間になったと思います。心に残った言葉がいくつもあり、これからも思い出すことになりそうです。会場となった長野県筑北村「冠着荘」の地をからヒントを得ながらも、引き続き身体と共に探求し続けたいことにも出会えました。
|