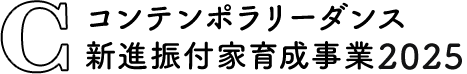言葉あるいはハザマ、余白、隙間の中から〜Choreographers2022 [沖縄公演] 対談企画「次代の振付家と沖縄の表現者によるダイアローグ」②山下残 × 西永怜央菜(アーティスト)
掲載日:2023/03/08

(左:山下残、中央:西永怜央菜、右:小川)
言葉あるいはハザマ、余白、隙間の中から
聞き手・構成:小川恵祐(舞台芸術制作者 / 沖縄アーツカウンシル・プログラムオフィサー)
原体験の記憶をたどる
小川:まずはお二人に、この分野で活動するきっかけから現在に至るまでを、簡単に教えていただきたいと思います。
西永:いまは現代アートの作品をつくっています。私はよくインスタレーションをつくっていて、切り絵をまず作って、それを影絵にして空間をつくります。切り絵の元になるのは、私自身が経験してきた日記的な出来事が多いです。なぜ切り絵かというと、自分は作家をやってるわりに手先が器用じゃないと思っておりまして。絵を描くというよりは、線を書く方が好きなようなんですよね。手癖が結構強くて。(切り絵では)カッターという道具によって、手の荒っぽい動きがある程度抑制されて丁寧な線をつくれたり、ときに思いもよらない手の動きになったり、そういう過程がおもしろいんです。カッターという道具の方が自分の存在を飛躍していけるような気がするので、自分から離れるためにその手法を使いつつ、自分の日記的な出来事に問題が収まっていくんですけど、(そこから立ち上がる)物語から、沖縄の歴史や、個人的な出来事の中にある社会性とか、「社会性」だけでは還元できないよく分からない何かを、受け取って貰えばいいなと思って制作しています。
小川:西永さんは今「やんばるアートフェティバル*1」にもちょうど切り絵を用いたインスタレーション作品を出展されています。一方で、切り絵だけでないさまざまな手法でこれまで作品を発表されてきたと思いますが、いまの手法に至るまでにどういった過程がありましたか?
*1 やんばるアートフェスティバル 沖縄県大宜味村にある廃校などをメイン会場に開催される、地域回遊型の展覧会。参照:https://yambaru-artfes.jp/
西永:私は沖縄県に90年代後半に生まれて、アメリカ軍が放送するテレビ番組を日常的に見ていました。ミュータントタートルズとかスポンジボブとか、アメリカのカートゥーンが好きで。それで、アメリカのアニメーションの線が、日本のアニメーションの線と全く違っていて、子どもの頃に衝撃を受けて。「この独特の線をどう表現したらいいだろう」と考えたときに、切り絵という手法を思いつきました。切り絵を使って、欧米の人たちからSNS上で「いいね!」をもらうのが「原体験」だったことを、最近思い出しました。
小川:山下さんは、現在のコンテンポラリーダンスを含むさまざまな活動の「原体験」のようなものがあるとすれば、どういったところにあったでしょうか?
山下:原体験でいうと、僕は 1970 年生まれで、(出身は)高度成長期の大阪の寝屋川市というところでした。隣の市には有名な電機メーカーの本社があって、周辺にはベットタウンが広がっていて。まさに「寝屋(川)」なので。人々が仕事しに出かけて、帰って寝る場所というようなところでした。その時代はどんどん自然が壊されながら、ニュータウンとして新しい団地や高層住宅が日々建っていっていました。自分がそこに育っていく過程の中では、周りにあった遊び場がどんどん無くなって、代わりに建物が出来ていくという時間的な環境だった。そういうなかで、ある日突然溜池ができたり、雑木林がはげ山になったり、何年もそのまま放置されているような状況があったり。今ほど大人が気を遣ったりしていなかったからか、(子どもが)工事現場の空き地で遊んでいるような環境が普通だったんですよ。ちょうど 1970 年代、自分が子どもの頃の原体験でいうと、自然が取り壊されて、同時に新しい建物が立っていくハザマ、水溜り、埋め立てした小高い山とか、空き地とか・・・。まさに今回の作品に関してのステイトメントにある、何もない空き地で遊んでいた、と。そういう原体験に、創作動機があります。
小川:このステイトメントというが、チラシにも書いてある「みなとみらい21がんばって24時間工事しているけど、解体も構築もできていない僕は、何もない空き地で遊んでいる子供がそのまま大きくなったようなもんだ。」という、山下さん自身の作家としての言葉なのですね。これについてはさまざまな解釈ができると思うのですが、西永さんは沖縄に90年代後半に生まれて、無くなっていく景色とか、そのなかの空き地や、ハザマや、そういった記憶ってありましたか?
西永:「ハザマ」かあ。自我が芽生えた2000年代前半の話になるんですけど、なんだろうな。現在の沖縄自体がハザマじゃないけど、子ども時代の沖縄県のイメージって「青い海と白いサンゴ礁で、ハイビスカスで、みんな笑顔でキジムナー*2 ありがとう!」ってかんじで。「ちゅらさん」ブームだったんですよね。テレビで「ちゅらさん」を見て、国営放送もなんのことか分からないから、「あー、沖縄県ってこういうかんじなんだ」と。原体験が「ちゅらさん」になっちゃって。
*2 キジムナー 沖縄諸島で伝承される精霊、妖怪。今日では、木(ガジュマル)に住み、赤い髪で背丈は人間の子ども程度というイメージで認識されることが多い。
小川:それは10歳くらいのときでしたか?
西永:5歳とかかな?空前の沖縄ブームが来てて、急速に眩しくてイケてる沖縄イメージがつくられていった時期で、自分の中の沖縄もそういうイメージで作られていった。でも、「あれ、なんか全然安らぎの島じゃないじゃん?」と、小学生くらいからだんだん気付き始めた。私が捉えていた沖縄はなんだったのか?あれは一体どこにあるのか?それもなんか、ハザマ的なものなのかなと、今の話を聞いて思いました。具体的な変化だと、那覇市にも米軍基地や自衛隊基地があって、基地が返還されて新都心というツルピカの真っ白なまちができて、モノレールもできてきて・・・と。それでいて、戦争経験者がどんどんいなくなっていっちゃう。義務教育だと、琉球王国とかの沖縄の歴史を学べないし。私は沖縄と本土の両方にルーツがあるんですけど、なんかこの歳でようやく「自分もそうだわ」みたいな。「ハザマしかないんですけど(笑)」みたいな気持ちで過ごしています。

©︎Arts Tropical
自分にとって一番遠いものへ
小川:『横浜滞在』という作品の話に踏み込んでいきたいと思います。あくまで映像資料ですが、西永さんには事前に今回の作品を見ていただきましたが、感想として、言葉に着目したとうかがいました。たとえばですが、昨今の現代美術においてはキャプションでの説明が求められるコンセプチュアルな作品が多くて、西永さん作品でも同様に言葉が重要になっているのではないかと思います。
西永:そうですね。
小川:一方で、作品を「どこまで説明して、どこまで説明しないか」という問題もあるなかで、言葉に着目されたのはどういう背景があるんでしょうか?
西永:言われてみると自分は、作品の中で言葉を使わざるを得なくなってしまったみたいです。言葉から離れられないのは、ちょっとひとつの悩みなんですけど。山下さんのインタビュー記事*3を読んでおもしろかったのは、言葉に近づいたり離れたりしていた、という点でした。もちろんX軸やY軸だけでなく、他にも三次元的な動きをしているとは思うんですけど、その距離のとり方が、羨ましいではないですけど、いいなって思いました。
*3 参照:国際交流基金による山下残インタビュー(聞き手・石井達朗[舞踊評論家]、2010.12.25)
https://performingarts.jpf.go.jp/J/art_interview/1012/1.html
西永:おもしろいところは、作者が発した言葉や音について「何が選ばれて、何が選ばれかったのか」というところじゃないかと、そういうことを考えていて。ただ、そこまでは頭で理解する話で。でもダンスって「みる」しかなかったので。一方で、この『横浜滞在』は、お客さんの反応込みで楽しめそう。いい意味で(観客としての)緊張を迎えるんだろうなって思います。一見、ヒップホップやラッパーがいるようにも見えました。沖縄はヒップホップも盛んで。ラッパーにはラッパーしか出せない謎の会場の雰囲気?分かんないけど、謎の言葉の使い方みたいな何かがあるだろうなと思っていまして、それをまた”なはーと”というあの新しい行政の劇場で上演されて、どうなるのか分からないんですけど、非常に興味深いですね。
小川:いまの一連のレオナさんの感想と言いますか、きっと、作品をご自身のなかに落とし込んでいく、その過程のようなものも見えたんですけども、それを聞いて山下さんはどのように感じられましたか?
山下:言葉について言葉で語るのってなかなか難しくてですね。メディアと身体についての 議論は自分がダンスの創作を始めた 90 年代から盛んにありましたが、その頃から何をメデ ィアとして用いるか、どういうふうに使おうか模索していました。僕は美術も好きなので影響を受けているんですが、たとえば美術館やギャラリーに行って望遠鏡が置いてあって、そこを覗いたその先に作品があるとか。あるいはベッドが置いてあって、ベッドの下を覗いたらその下に作品が展示してあるとか。そういうふうに、いろんな作家さんによって見せ方や方法があると思うんですけども、その望遠鏡だとかベッドだとか、作品を見るためのひとつの「仕掛け」みたいなものが自分にとっての「言葉」なんですよね。
ダンスの振付に、言葉を用いる
山下:最初に西永さんから「自分は作家をやってるわりに手先が器用じゃないと思っている 」という話や、「カッターという道具によって、手の荒っぽい動きがある程度抑制されて丁寧な線をつくれたり、ときに思いもよらない手の動きになったりと、自分から離れるためにその手法を使う」という話がありましたが、僕も創作を始めた頃は、ダンスは自分にとって一番遠いものだと思っていたんですよね。得意なことじゃなくて、不得意なことをやるって いうのは、作品や表現にとって大切だと思っていたので。「まさか自分がダンスなんて!」 というふうにダンスを始めたところがあるから。だから、ダンスは自分の得意でないものでした。次に得意でないのが言葉。けれど、それが見様によっては「なんて饒舌な奴なんだ」 と思われるのは仕方ないことかなと思います。言葉では伝えきれない要素が身体には色々 あるのに、一つの言葉を選んでしまっている、そういう不釣り合いさとか、暴力性とか、そ ういうところに敏感になって、ダンスの振り付けに言葉を用いている、そんな感覚です。
西永:自分は、『横浜滞在』は見た目の第一印象でなんとなくヒップホップを連想したんですけど、なんかヒップホップってそのなかでビートに言葉を乗せていくみたいなかんじじゃないですか?けど『横浜滞在』の場合は、ビートに値するのが「言葉」で、ラップがダンスになるのかな?もしかしたら逆かもしれない。分からないですけど、そういう(作品を)読み取るっていうか、読み取れる / 読み取れないじゃなくて、こっち(観客)が崩されていくって、すごい楽しいことだと思います。よく演劇や音楽のリサイタルなんかを観に行ったりするんですけど、お客さんのこと込みで作品をみた、みたいなところが私にはあって。たとえば、お客さんが携帯電話を鳴らして周りの人も気まずくなっていたり、そういう変なコミュニケーション?自分はそっちの方がおもしろいなって思ってるところがあるから。劇場の人からしたら不本意かもしれないけど、お客さんの反応や身体の所作も込みで込みで作品を見てみたいなって。それが私がやってみたいことだと思います。
小川:今、「観客」の存在についての話もありました。山下さんにお聞きしたいのですが、3月12日の那覇公演では、沖縄の人々にとってこの作品はどのように響く、あるいは、どのように響いて、共有されてほしいと思っていますか?
山下:「なんで横浜なのか」とか「ダンスでこれはありなのか」みたいな、なんかそういうふうにも感じられる方もいるでしょうし、そこを受け止めてもらえるキャパシティを期待します。やっぱり一番嬉しいのは、この作品を見て「あ、こういうことを自分でもやってみ たいな」って思ってくれるアーティストが生まれることです。それが一番嬉しいですね。
小川:なるほど。
山下:『横浜滞在』って、やっぱりどこか横浜の話だから他の場所でやることにちょっと躊躇する面もあって。だから実は、若干アレンジをして、大きな内容は変えずにその具体的な地域名を発表する場所の名称に変える、みたいなことを何度かやっているんですよ。でも、オリジナルのかんじっていうのはやっぱりね、自分にとってなかなか代えがたいので、そのまま沖縄で発表させてくれる皆さんにすごく感謝もあります。
西永:地名を変えているっている話、なんかバンドのライブとかでもめちゃくちゃ盛り上がりますよね。あと、自分がそういう問題意識があるんですが、「沖縄ナイズド」されているというか、「沖縄セレクト」?どうしても、アーティスト同士で集まって話したりすると、なんかその、沖縄の話から出られないみたいなのがあって、実はめちゃくちゃ悔しい。意図せずに縛られてしまって、「またしても!はぁ!」みたいなのがあるんで。だから、那覇でこの「横浜」ってワードが入っている作品を見れるって案外ないんですよね。逆にいいのかもしれませんね。地名にめちゃくちゃ接続される作品とも全然限らないと思うんですけど、あまり自分が意識的にできない「スイッチの切り替え」みたいなのをしてくれるの、ラッキーだなって思います。

©︎山下残
不完全な身体のハザマ、余白、隙間に生まれるもの
小川:最後にお二人から今後の展望、あるいはこれからの新しいダンス表現、これから新しい現代美術の表現を、ご自身の活動に触れながらお聞きしたいなと思います。
西永:私の場合は、「生きづらさ」って言ったら簡単すぎるな・・・得体の知れない何か違和感みたいなのがずっとあって。最近は発達障害が気になっていて、「そもそもどこからカウントされるの?」って。「どこからが発達障害で、どこからが違うんだろう」って、そのハザマに関心がいったんですよ。発達障害は近年ブーム化していて、社会的な発達障害への眼差しがすごい勢いで形成されてますけど、文化や地域が変わればそれが「発達障害」とは認識されないともいわれます。でも日本ではどうしても「平均」を求められてしまって、どこか変わってる人や、これまであまり意識されてこなかった人らが、そうではないとされてしまう。運動障害(と認識された身体)があれば、「挙動不審」とか、そういう言葉にその動きが名付けられてしまう。自分も、人前で緊張してしまうことを弱点だと思っていて。でも、いろいろ掘り下げていくと、これは生理現象なんだよなぁ、と。障害って以前に、身体のなかで何が起こってるのかを噛み砕いていくと、得体の知れない「障害と思しきもの」ではなくなっていく。人間が人とコミュニケーションする社会の中で、「身体」というものがどうやって動いてしまうのかを見たいし、知りたい。「なんでこの身体の動きをしてしまうのか」、「なぜこの動きをしたいのか」を、言語化じゃないけど、掘り下げていきたくて。それもあって、人の身体の動きに関心が出てきています。劇場でダンスを見たいとか思うようになって、お客さんが変な緊張をしたり、喧嘩したり、寝ちゃったりするのを観察するのが楽しくなっちゃったみたいな、そういう感覚を持ちながら作品をみたいし、自身の制作のヒントにもなり得るんじゃないのかなと思いますね。
小川:先ほど山下さんは「自分でもやってみたい、と思ってくれるアーティストが生まれることが一番嬉しい」とおっしゃっていましたけども、今後のこれからのご自身の活動や、あるいは「沖縄」という地域のに焦点を当てた時の、ダンスやその他の表現の今後の展望のようなものがもしあれば、教えていただきたいなと思います。
山下:パンデミックが明けようとしている今でも、なかなか未来の展望は立てにくくて。 そんななか、数日前に言語を使ったあるワークショップに参加しました。それは、自分たちが無作為に 選んだアルファベットの単語で詩を作りましょう、という内容で。そこで、ある参加者の学生がチャットボットっていう、AI の自動文章生成プログラムをパソコンから取り出して、「今みんなでやっていることは、これで簡単に出来ちゃうよ」みたいなかんじで教えてくれました。 AI の 文章能力って無作為の単語で詩をつくるといっ たような創作の場面には本当に優れていて、 完璧で。そこで「言葉と身体」ということを考えた時に、まさに西永さんの話にあった発達障害とか、そういう価値観っていうのが見直されるような世の中になるのかな。言葉が合っているか分からないんですけども、何かこう欠落したものであるだとか、それこそハザマだとか、完璧でないものの隙間や余白みたいなものが、もっと表現のなかに生かされてくるだろうなって 思いはあるんです。「優れたアート」って言っていいのか分からないけど、そういうものはどんどん 勝手にプログラミングされていくだろうから、あとはそれらが自分たちの身体とどう拮抗するのか。どう一緒に生きていけるか。今現在のどこかで勝手に決められた基準の中に、及ばない身体であるとか、余白を埋めきれない能力だとか、そういうところに新しい何かがあるかなっていう期待はしています。本当に先のことは全然まだ予測がつかないですけども。
西永怜央菜 Reona NISHINAGA
幼少期より沖縄本島、宮古島、ホーチミン、秋田県と住居を転々とする。自身の家族史の収集や子供時代の記憶を糸口に作品制作を行う。 2020年沖縄県立芸術大学大学院造形芸術研究科修士課程環境造形専攻修了。 主な展覧会に個展「ハロウィーンの子供たち」(Arts Tropical/沖縄、2019年)、「PORTABILITY」(HAPS/京都、2019年)、「OKIMIYAGE」(オルタナティブスペースHESO/山形、2021年)、「沖縄人」(gallery rougheryet/沖縄、2022年)がある。
Instagram:@sionarh
山下残 Zan YAMASHITA
1970年大阪府生まれ。主な作品に、100ページの本を観客に配りページをめくりながら本と舞台を交互に観る『そこに書いてある』、スクリーンに映写される呼吸〈すう・はく〉の記号と俳句から引用されたテキストと生の身体の三要素を時間差でリンクさせる『せきをしてもひとり』、本物の線路の上で断片から成る世界の事象をつぶやく『大行進』、バリ島からのオンラインレッスンを通じてバリ舞踊を習う『悪霊への道』、無血革命と呼ばれた2018年マレーシア国政選挙を現地取材した記録作品『GE14』、身振りや台詞の全ては対面する相手からの承諾が必要である『インビテーション』などがある。
>>プロフィール詳細
https://choreographers.jcdn.org/artist/1494
https://choreographers.jcdn.org/program/choreographers2022_okinawa