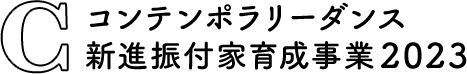投げ捨てて、つくる〜Choreographers2022 [沖縄公演] 対談企画「次代の振付家と沖縄の表現者によるダイアローグ」③ 横山彰乃 × 中村亮(ドラマー、作曲家)
掲載日:2023/03/31

(左:横山彰乃、中央:中村亮、右:小川)
投げ捨てて、つくる
聞き手・構成:小川恵祐(舞台芸術制作者 / 沖縄アーツカウンシル・プログラムオフィサー)
その言葉自体が、もともと存在しなかった
小川:横山彰乃さんのこれまでの活動については、すでに“Choreographers”の公式ホームページ*1に素晴らしいインタビュー記事がありますが、あらためてこの分野で活動をするきっかけから現在に至るまでについて、簡単に教えていただければと思います。
彰乃:私は長野県の田舎の山奥の出身で、小さい頃に習い事としてダンスを始めました。それがいわゆるコンテンポラリーダンスとか、ストリートダンスやバレエではなかったんです。「コンテンポラリーダンス」って初めて聞いたのが高校生ぐらいだったんですけど、あんまり(ジャンルの)違いが分からなくて。でも、踊り続けたかったから大学進学で上京して、そのまま活動拠点が関東首都圏になってるというかんじです。コンテンポラリーダンスをやっているって意識はあまりなくて。劇場で長めの作品をダンスでつくるとなると、結果的にそういう括りになってるっていうだけで、今の活動をしています。
亮:彰乃さんのお話を聞いていてちょっと似てるのかなと思ったのが、自分も「ドラマーになりたい」とか、そういう考えがあったわけじゃなくて。高校3年からアメリカに留学した理由は、自分の進路が分かんなかったから。いろいろなことをゼロにしたくて留学したんですよ。小さい頃からクラシック音楽をずっとやってて、それをやめるために留学して。それでクラシック以外の音楽学校があるって聞いて、そこに見学に行ったのが17歳の時。そこでいわゆるファンクとかR&Bといったブラックミュージックと出会って、自分の人生を賭けてやりたいなって思ったのが、今の活動のきっかけですね。ただ、「これで自分の人生は飯食っていくぞ!」とか、そんなことは全く考えなかったです。
彰乃:プロでやっていくっていう気持ちが最初はなかったというのは、すごい分かります。はじめにファンクやR&Bとの出会いがあって、それが今の活動のきっかけになって、そこからジャズを始めたのは、何か「これだ!」っていうのがあったんですか?
亮:めっちゃあったんですよ。27歳のときにニューヨークに住んでいて、脳腫瘍で倒れたんですよ。病院に行ったらデカい腫瘍があって。後頭部の小脳に。ガンではなかったんだけど。それで手術したら、もううるさい音が聞けなくなって。しかも、ドラムの入ってるビートの音がうるさくて聞けなくなってて。それに、ドラムの練習をするにも簡単に腕が動かせない。となると、もう指の練習しかできなくなって。指の練習は、ジャズの人がよくやる、小さいボリュームの奏法を訓練するためのものなんですよね。2回目の手術の後に回復して。そっからですね。ジャズやろうって思ったのは。
彰乃:珍しいですね。音楽もそうだし、いろいろなことって大体、何か聞いたり見たりして影響を受けて、やりたいと思うものじゃないですか?でも、身体が原因になったというのはなかなかおもしろいと言いますか、すごい大変だったと思いますけど。
小川:亮さんはそういった青天の霹靂というか、人生が一変してしまうようなことがかつてあった中で、それでも現在もジャズやドラムに特別な思いで向き合い続けられているのはどうしてですか?
亮:先ほど彰乃さんが、「コンテンポラリーダンス」とかいうジャンル分けについて、そんなに考えていないって話があったのと、たぶん同じように自分も今ドラムと向き合っていて。俺は「ジャズ」ってものをジャンルとして捉えていなくて。マイルス・デイヴィス*2っていうトランペッターがいるんだけど。
*2 マイルス・デイヴィス Miles Davis(1926-1991) アフリカ系アメリカ人のジャズトランペット奏者、作曲家、編曲家。クール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズ、エレクトリック・ジャズ、クロスオーバー、ヒップホップ・ジャズなど、数多くのライヴ活動やレコードアルバムを発表し、「ジャズの帝王」と称される。
亮:彼の伝記がすごい面白くて。彼によれば、「ジャズ」って言葉自体もともと存在しないんですね。「白人が金を稼ぐために勝手に名付けた。俺がやってるのは音楽だ」って言っていて。自分もそう思って、だからジャズって音楽を今大好きなんだけど。「◯◯年代の様式が好き」とかそうではなくて、それぞれの「あり方」に対して、俺は「ジャジーJazzyだ」って言葉をよく使う。だから変な話、自分はクラシックの演奏を見ても「この人、ジャジーだな」って使ったりするわけ。だからやっぱり、その場にいるってこと以外に特に決められたことはなくて。そのために毎日練習してる、というか・・・。「投げ捨てるために、ステージに立つ」、それがジャジーだなって俺は思う。

©︎Akira_Nakamura
違和感からはじまるダンス
亮:小さい頃ダンスに触れた時に、どんなジャンルのものでもなかったという話をしてましたが、一応すべてのジャンルに歴史と今の流行りとかがある中で、俺から見たらコンテンポラリーダンスって「なんでもオッケーよ」って言ってるよなって。そのうえで、自分が自分なりに見聞きしてきたなかで、覚えておきたいと思うものってあるんですか ?
彰乃:もともとやっていたのはモダンダンスっていう、一応ジャンルがあるものだったんです。でも小さい頃に「モダンダンス」とか言われても何も分かんないじゃないですか。師匠もちょっと変わった人だったんで、日本のきれいに踊る現代舞踊みたいなものでもなく。今みたいにインターネットはないし。でも、なんか小さい頃って変な動きするじゃないですか?小さい頃はそういう感じで、部屋で音楽を流して踊っているのが好きだったんですね。今みたいに、テレビでダンスを見るということもなかった時代なので。音楽に「ノる」なんて知らないし、長野の山奥でそんなの見たことない。でも、なんかその(小さい頃の)感覚は自分の中にあるんですね。
亮: 今は特に、 SNSやインターネットで流行った形をみんな真似をしますよね。技術的にはいいこともあるのかもしれないけど。「個性」と言ってしまったら簡単に聞こえるかもしれない。けれど、みんななんかパーソナルレスで、とにかく表面的なところだけっていうのが増えてる気もしてて。「ダンスやってますよ」って言われて(劇場に)行って、みんなたぶん毎日見てるYouTube とか SNS のことを想像して見に行くと思うわけ。そしたら観客を呼ぶためにはそれをやるしかなくなっちゃうっていう。音楽も全く一緒で。興味ない人達には全く響かないものになるっていう、そのへんが今の時代難しいなって思うことが多いですね。
小川:今の亮さんの問題意識は、今回の作品のステイトメントにもすごく共鳴していると思いました。そのあたり、彰乃さんに詳しくお聞きしたいです。
彰乃:まさにインターネットの話なんですけど、今って SNS のおかげでいろんなところの遠くの国の情報を見れますよね。それで、この作品をつくったのが2018年の暮れから2019年の頭だったんですけど、フランスでテロ事件があったときに Facebook かなんかのアイコンがみんなフランス国旗にできたじゃないですか*3。ブラック・ライブズ・マター*4でもそうでしたよね。
*3 2015年11月、フランス・パリでおよそ120人が亡くなった同時多発テロが起きた。当時のフェイスブック社は哀悼を目的に、アカウントのプロフィール画像にフランス国旗のトリコロールを重ねるキャンペーンを企画した。事件直後には、いわゆるイスラム過激派組織の一斉摘発が行われている。
*4 ブラック・ライブズ・マター(Black Lives Matter) 2020年に起きたアフリカ系アメリカ人に対する警察の残虐行為を主なきっかけにアメリカで始まった人種差別抗議運動のこと。フェイスブックで事件の動画が拡散されたことで世界的にムーヴメント化した一方で、差別的な投稿や陰謀論も同時に拡散したことが社会問題となった。
彰乃:そのスピードがすごすぎて。特に日本にいる日本人はそこにいない人ばかりなのに、何か貼って(SNSのアイコンが)変わっていっているのを見たりして。殺人をよしとしてはいけないんですど、複雑な背景がいろいろあるから、そういうことを調べてアイコン変更してるのかな?ってすごい疑問を持っちゃって。そういうのを気にし始めたら、何かお題を出されたらそれに乗っかって、忘れたら次のが来て、また乗っかってっていう・・・。そんな情報の波に、当事者ではない人たちが次から次への乗り換えていくのが「ムカつくな」って。そういうタイミングで、たまたまツアーでいろんなところの海を見て、そのときにそれが一番違和感があることなんだなって気づいたのが、今回の作品の創作のスタートだったんですね。
小川:チラシの裏面にはステイトメントとして「よく知っている底から / 水面を見上げ / 知らない水平線を / 思い浮かべず / 音の届く先まで睡り / どこかの花を想う」と記載されています。ですが一方で、けっこう今ってアーティストの方にもそういう表明?説明みたいなものがすごく求められるようになっている気がします。
彰乃:それもすごい嫌なんですけど。
小川:僕みたいな人に対談してくださいとか言われてしまって・・・
彰乃:全く説明しなくてもいいし、してもいいと思ってるんですけど。別に、対談やなにかで話すのはいいと思っていて(笑)。ただ、チラシとか当日のパンフレットに「もうちょっと分かりやすく書かないと」というふうになってきちゃうと、そこに書けるならもはやダンスは・・・って。「正解を見せるわけじゃないのにな」っていうのがあるので、そこは作家の文章をもっと工夫すればいい話なんですけど、分かりにくすぎてもよくないなと思いつつ。なんかこう、現代はめちゃくちゃ分かりやすさや説明を求められているのをひしひしと感じているので、こういうものをやってる私達はけっこう立場がギリギリな感じが、すごい。
亮:「正解を見せるわけじゃないのに」と彰乃さんが言ってたのがまさしくそうで。学校の教育が美術にしても音楽にしても、理解を求めることを小さい頃から言われると、なんか、このダンス作品の何を楽しめばいいんだろうかって。この、目の前で起きてることじゃなくて、なんか他に探しちゃって、そしたら「見てないじゃん」って言いたくなることがあるから。
彰乃:そうですね。国語の授業で「この作者は何が言いたかったでしょうか?」みたいな問題って普通にあったじゃないですか?それって日本特有の問題らしくて。自分が思う感想っていうよりも、この作者が何が言いたいのかを探し出すっていう教育。だから、分かんないものを見た時に「こわい」って思っちゃう人がすごい多いんですって。
亮:よく思うのが、公演を制作する人たちが「良いものだ!」ってつくろうとしすぎてる感が個人的にある・・・とかは(この記事に)書かなくてもいいけどね。
小川:なるほど。
亮:実際に舞台に立ってる人たちは、もっと任せられるつもりで(舞台に)立っている気もしてて。だから、広報宣伝の仕方とかも「自由に遊びに来な」って。自由な感覚で来たらいいんじゃないって言ってみたら、めちゃくちゃおもしろいと思うわけ。
小川:(現地制作として)反省しました。
一同:(笑)

©︎横山彰乃 / lal banshees
「銭湯行ってきなよ」
彰乃:私の振付ってほとんど決まっているんですけど、「すべて忠実にやってください」っていう指示は一切出さないんですよ。ユニゾンという同じ動きをするときでも、形というか、すごい細かく直すことはあったとしても、演出的な指示はあんまりしなくて。「このシーンは、苦しいシーンだから苦しそうにやって」とは言わずに、「もうちょっと体の感覚がピリピリするかんじで」とか。あとは、「やってみてどんな感覚でしたか?」とダンサーとやりとりしたり、ダンサー自身に説明してもらったり。「説明しなくていいんで、勝手にやってください」と言うときもありますし、逆に言うと、その方向は違うかもしれないって修正していくときもあったり。ダンサーそれぞれ感じてることが違うってことがやりたくて。
亮:どうしても聞きたかったのはそこなんですよ。一人のエネルギーでやるのではなくて、多人数でやる。でも、それは自分が作った作品で、「こんなことになるんだ」という嬉しさもあれば、「こんなにしかならないんだ」とかってある種の葛藤があると思うんだけど、「これはこれでいいんだ」ってどう線引きするのかが気になって。
彰乃:まず、私の中で作る振付というものよりも、人の身体の方がおもしろいと思っていて。プレイヤーとして自分で踊ることとは別に、動きを作ることも好きで。「アテ振り」って音楽にもありますかね?
亮:あります。
彰乃:人の身体を見ながら作って、「この人の腕だったら、次こうなったらおもしろいな」って作っていくんですね。線引きではないのですが、自分は、その人がいて、その人を見ながら作っていくのが得意です。演出というか、踊り方とか立ち方については、私がこうやって欲しいと言っちゃうのは違うなって思っていて。考えてもらうようにはするのだけど。たとえば仕事のように「これを完全に再現してください」だったら、答えや形を求められているのでそれを言ってしまいますが、自分の作品に関してはそれはやらない。私が答えを決めつけてその人にやらせてしまうことになるから、その人じゃなくてもいいってことになってしまう。なので、できるだけその人に気づいてもらう。クリエーションをやろうとして、もちろんうまくいかないなってときもあって、さっき亮さんが言ってた「放り投げる」感覚も必要だと思っているので、若いダンサーの子に伝えるのに、「ちょっと一回銭湯行ってきなよ」とかって言うんですけど。
亮:あはは(笑)
小川:え、どういうことですか?
彰乃:めちゃくちゃ熱いお湯に入った後に、冷たい水風呂に入った時、なんていうかな、刺激?みたいな意味で・・・それはちょっとズルなんですけどね。たぶん、脳に分泌される成分は一緒だろう、みたいなかんじで。
亮:めっちゃいいアドバイスだと思いますね。
彰乃:別にアーティスティックな意味じゃなくて、「川に入ってこい」みたいな。
亮:実際にね。
彰乃:そういう感じ。
小川:?
亮:でも、言葉って難しいよな。ダンスって何?って話だし。もともとは・・・ま、いいや。こんな話は今度飲みながらしましょう。
一同:(笑)
中村 亮 Akira NAKAMURA
ドラマー/作曲家。1979年沖縄県那覇市出身。幼少期よりバイオリンとピアノを学ぶ。1998年にバークリ音楽大学入学。卒業後、Bostonを拠点にプロ活動を開始。David Fiucyzinski,、上原ひろみ、Sam Kininger等多数のミュージシャンと共演。2004~2005年中国上海にて演奏活動、2006年より再びアメリカに拠点を移す。2009年東京へ移住。JUJU、Monday満ちる、三浦大知、ナオトインティライミ、ハナレグミ、さかいゆう、Nao Yoshioka、サラ・オレイン等と共演。そのほかミュージックディレクター、プロデューサー、アレンジャーとしても活動。2015年拠点をドイツ、ベルリンへ。4年間の活動を経て2019年に帰沖。現在沖縄では演奏活動と並行して音楽事業のディレクターなども行っている。
横山 彰乃 Ayano YOKOYAMA
長野県大町市出身。舞台活動と並行し、演奏家やバンドとのパフォーマンスや、ライブ、MVへの振付を行う。東京ELECTROCK STAIRSのダンサーとして国内外の全作品に出演(2009-19)。2016年、ダンスカンパニーlal bansheesを立ち上げ。情景を意識した空間作りと、音との繫がりのある緻密な振付で、性別に囚われない中性的なダンスを創作。派生し感覚に着目した独自のムーヴメントを追求する。見落として通り過ぎてしまうような現実をファンタジックに切り取り、そして現実に戻す音楽的ダンスを体現する。
https://choreographers.jcdn.org/program/choreographers2022_okinawa